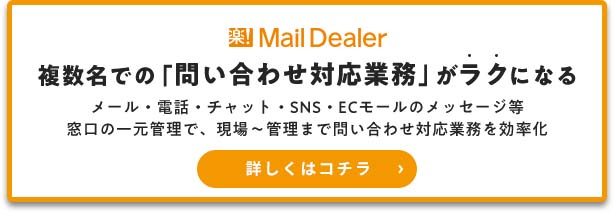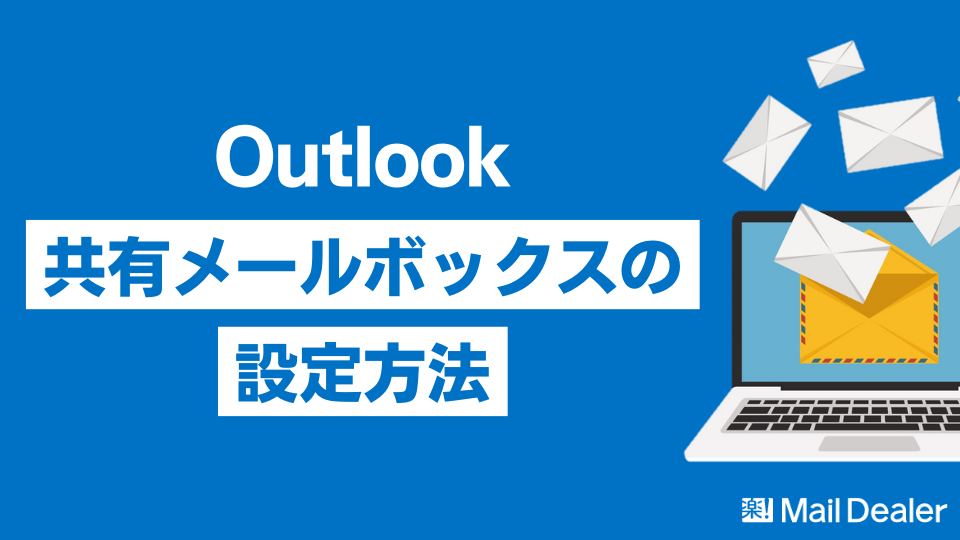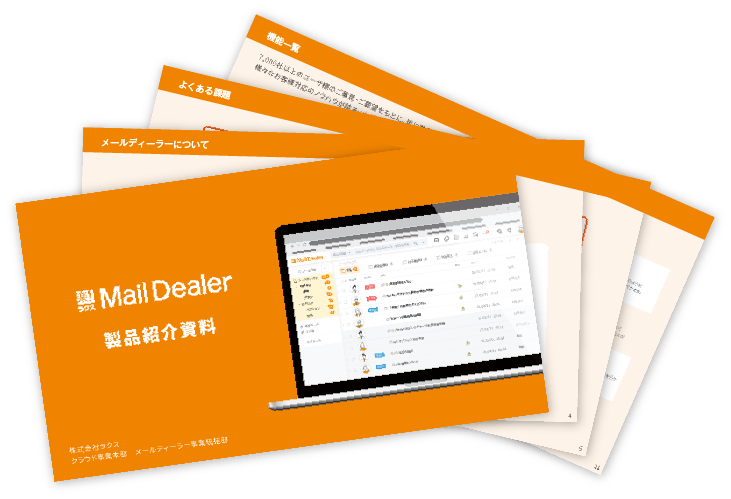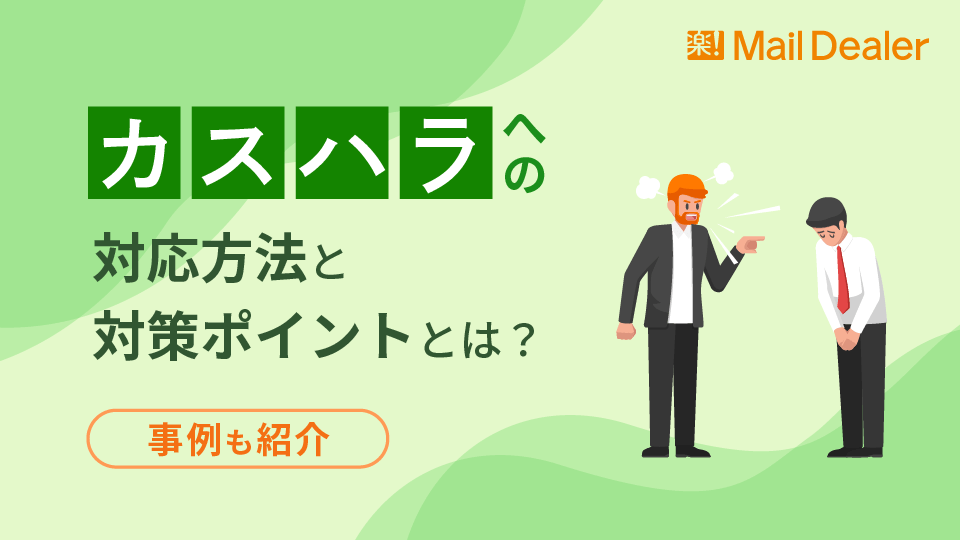
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、近年多くの企業やスタッフにとって深刻な問題となっています。顧客による理不尽な要求や暴言は、業務の遂行に大きな支障をきたし、スタッフの精神的負担を増大させる原因となります。企業にとって、カスハラへの適切な対応策を講じることは、スタッフの労働環境を守るだけでなく、顧客満足度を維持するためにも重要な課題です。
本記事では、カスハラの定義から具体的な対応方法、そして実際の事例まで、企業の担当者が知っておくべき情報をご紹介します。
カスハラとは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が自分の要求を過剰に押し付ける行為や、スタッフに対して不適切な言動を行うことを指します。これは、スタッフに対する精神的な圧力や業務の妨害を引き起こし、場合によっては身体的な被害をもたらす場合もあります。具体的には、暴言や過度な要求、土下座を強要する行為、店舗での居座りなどが代表的なカスハラの事例です。
カスハラは、単なるクレームや不満とは異なり、顧客が感情的になり、他者に対する尊重を欠いた行動を取るのが特徴です。このような行為は、スタッフの業務効率を低下させるだけでなく、企業の評判や職場環境にも悪影響を及ぼします。また、カスハラが発生すると、スタッフはストレスを抱え、仕事の意欲を失う場合もあります。
企業は、カスハラに対する明確な対応策を定め、スタッフに対して適切な教育が求められています。顧客との良好な関係を築きつつ、理不尽な要求に対しては毅然とした態度での対応が重要です。
カスハラの種類と例
カスタマーハラスメントにはさまざまな形態があり、その中には明確な犯罪行為に該当するものも含まれています。以下では、特に重要な5つの犯罪類型について、具体的な事例とともに詳しく解説します。
脅迫罪に該当する可能性のあるカスハラ
脅迫罪は、相手に対し生命、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えることを告知して、不安や恐怖を与える行為を指します。カスハラの文脈では、たとえば「従業員の個人情報をばらまくぞ」「家族の住所はわかっているんだからな」といった発言が該当する可能性があるでしょう。また、「商品の不具合で怪我をしたことを報道機関に通報する」といった内容をほのめかすことも、脅迫罪に該当する可能性があります。
近年では、対面での直接的な脅迫だけでなく、メールやSNSを通じた脅迫も増加しています。「ネット上であなたの悪評を広めてやる」「個人情報を拡散させる」といった書き込みも、脅迫罪として扱われる可能性があるので注意が必要です。このような行為は、たとえ実行する意思がない場合でも、相手に不安を与える時点で犯罪が成立する可能性があります。
恐喝罪に該当する可能性のあるカスハラ
恐喝罪は、脅迫によって相手から財物や財産上の利益を得ようとする行為です。たとえば、「賠償金を払わないと、あなたの会社の悪評をSNSで拡散する」「商品を無料で提供しないと、マスコミに告発する」といった要求がこれに該当します。また、「気に入らない接客をされたから金を払え」という要求も恐喝罪となる場合があるでしょう。
特に注意が必要なのは、一見正当な苦情や要求を装って行われる恐喝です。「商品に不具合があったから賠償しろ」という要求に、実際の損害額を大きく超える金額を要求したり、事実と異なる被害を主張したりするケースがこれに該当します。
強要罪に該当する可能性のあるカスハラ
強要罪は、暴行や脅迫によって、相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする行為です。カスハラの場面では、「謝罪文を書け」「土下座しろ」という要求の強制が該当します。また、「今すぐ社長を呼べ」「担当者を代えろ」といった、通常の業務手順を無視した要求の強制も強要罪となる可能性があります。
特に深刻なのは、スタッフの人格を否定するような要求を伴う強要です。「お前なんかクビになればいい」「二度と接客するな」といった発言とともに、特定の行為を強制するケースは、強要罪として扱われる可能性が高くなります。
威力業務妨害罪に該当する可能性のあるカスハラ
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することを指します。具体的には、大声での罵声、執拗な電話攻撃、業務を妨げるような居座り行為などが該当します。たとえば、「対応が気に入らない」という理由で店舗内で大声を出し続け、他の客の対応ができなくなるような状況を作り出す行為は、威力業務妨害罪として扱われる可能性があるでしょう。
また、特定のスタッフに対してしつこく電話をかけ続けたり、大量のメールを送りつけたりするなど、通常の業務が行えない状況を作り出す行為も該当します。SNSやレビューサイトでの組織的な誹謗中傷により、企業の業務を著しく妨害するケースも、威力業務妨害罪として問題になる場合があるでしょう。
不退去罪に該当する可能性のあるカスハラ
不退去罪は、正当な理由がないにもかかわらず、他人の建造物などに侵入し、また要求されても退去しない行為です。たとえば、営業時間が終了したにもかかわらず、「納得いく説明を受けるまでは帰らない」と店舗から退去しないケースや、オフィスに押しかけて「責任者と話がつくまでここを動かない」と居座り続けるような行為が該当します。
また、入店制限や営業時間短縮を行っている場合に、これを無視して強引に入店を求めたり、閉店時間を過ぎたりしても退去しないといった行為も、不退去罪として扱われる可能性があるでしょう。このような行為は、スタッフの労働時間や休憩時間を侵害するだけでなく、他の顧客へのサービス提供にも支障をきたす深刻な問題となります。
企業はカスハラに対応する必要があるのか?
では、企業はカスハラに対してどの程度対応する必要があるのでしょうか。ここでは、対応の必要性についてご紹介します。
防止措置の義務がある
企業がカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)に対応する必要がある理由の一つとして、防止措置の義務が挙げられます。スタッフが安全で健康的な労働環境で働けるよう、企業には労働安全衛生法や労働契約法に基づき、その環境を整える義務があるのです。
カスハラは、単なるサービス提供者と顧客との間の摩擦ではなく、労働者に精神的・身体的な負担をもたらす深刻な問題として認識されています。スタッフが顧客からの過剰な要求や暴言、ときには身体的な攻撃を受けると、ストレスや不安が増大し、結果として労働意欲の低下や健康問題が生じることが多く報告されているためです。このような状況を放置することは、企業にとって重大なリスクとなり得るでしょう。
また、企業が適切な対応を取らない場合、スタッフが被害を受け続けると、職場環境全体に悪影響を及ぼす可能性があります。他のスタッフが同様の被害を恐れ、業務を遂行する上で不安や恐怖を感じるようになると、チーム全体の士気が低下し、パフォーマンスにも影響を及ぼすでしょう。その結果、企業は生産性の低下や離職率の上昇という経営課題に直面することになります。
さらに、スタッフが職場環境の改善を求めて労働組合や労働基準監督署に訴えた場合、企業の法的責任が問われる可能性も高まるでしょう。このようなリスクを未然に防ぐためにも、カスハラ防止に向けた措置を講じることは、企業として避けられない義務であると言えます。
具体的な防止措置としては、カスハラに関する明確なルールやポリシーを策定し、スタッフにその内容を徹底的な周知が挙げられます。また、スタッフがカスハラを受けた場合に適切に報告できる仕組みを整えることも重要です。この際、報告が行いやすい環境を構築するために、匿名での相談が可能な窓口の設置や、被害者が二次被害を受けないよう配慮した対応が求められます。
さらに、報告を受けた際の具体的な対応策や、その結果に基づく改善計画を明確にすれば、企業がスタッフの安全を守る姿勢を示せるでしょう。
厚生労働省の指針
厚生労働省はカスハラ問題の重要性を認識し、企業が取るべき対応について具体的な指針を示しています。この指針では、企業がスタッフを保護するために必要な措置を講じる義務を明確化しており、事業主には積極的な関与が求められています。特に、パワーハラスメント防止措置が2020年6月から大企業に義務化されたことを受け、顧客からのハラスメントへの対応もその一環として重要視されているのです。この法律は、中小企業にも2022年4月から適用されており、企業規模を問わず、カスハラ防止への取り組みが求められる時代に突入したと言えるでしょう。
指針では、第一に、顧客との接触が避けられない職場において、事前にリスクを洗い出し、そのリスクを最小限に抑えるための計画を立てることが強調されています。これには、カスハラの定義や具体例をスタッフに教育し、問題が発生した際に迅速に対応できるスキルを身につけさせるなどが含まれます。たとえば、冷静な対応方法や、危険を感じた場合に顧客との距離を取る手段などが挙げられるでしょう。
厚生労働省の指針に基づき、企業が実効性のあるカスハラ防止策を講じることは、スタッフにとって働きやすい職場環境を維持するための重要な要素です。これにより、企業は長期的な信頼関係を構築し、持続可能な成長を実現する土台を築けるでしょう。
カスハラへの具体的な対応方法
では具体的に、カスハラにはどのように対応すれば良いのでしょうか。ここでは、カスハラへの具体的な対応方法をご紹介します。
まずは相手の話をよく聞く
カスハラへの対応の第一歩として、相手の話をよく聞きましょう。クレーム対応において、顧客が自身の不満や意見を聞いてもらえば、感情が和らぐケースが多々あるとされています。特に、相手が感情的になっている場合、相手の言葉を遮らずに最後まで話を聞く姿勢を見せれば、相手との信頼関係を築く第一歩となるでしょう。
このプロセスでは、相手の意見に同意する必要はありませんが、共感を示すような応答を心がけると良いでしょう。たとえば、「そのような状況でご不便をおかけして申し訳ありません」といった言葉を使えば、相手が自分の気持ちを理解してもらえたと感じるケースもあります
ただし、相手の話を聞く際には冷静さを保ちましょう。相手が高圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりする場合もありますが、感情的に反応すると事態が悪化する恐れがあります。そのため、相手の言葉に耳を傾けつつ、自分の感情をコントロールし、相手の不満の根本的な原因を探る努力が求められます。
理不尽な要求は受け流す
相手の話を聞くことが重要である一方で、理不尽な要求には毅然とした態度で対応する必要があるでしょう。すべての要求に応じると、企業側のリソースを圧迫するだけでなく、他の顧客やスタッフに不利益を与える可能性もあるためです。理不尽な要求とは、サービス範囲を超えた要求や、スタッフ個人を傷つけるような内容を含むものを指します。このような場合、相手の要求に正面から反論するのではなく、受け流せば、状況を冷静に保てるでしょう。たとえば、「その件については確認が必要ですので、少しお時間をいただけますか」といった対応が効果的です。
また、理不尽な要求に対応する際には、企業の方針やルールを基にした対応が重要です。スタッフが一貫した対応を行えば、顧客が過剰な要求をエスカレートさせるリスクを減らせるでしょう。
書類の作成や署名、捺印はしない
カスハラへの対応において、相手の要求に基づいて書類の作成を行ったり、署名や捺印を求められたりした場合には、応じないことが基本です。これらの行為は法的責任を伴う可能性があり、後々企業やスタッフにとって不利な状況を招くリスクがあるでしょう。たとえば、書面に署名すると、相手の主張に同意したと解釈される場合があります。そのため、このような要求があった場合には、上司や法務部門に相談し、慎重に対応する必要があるでしょう。
署名や捺印を拒否する際には、相手に対して冷静かつ丁寧な説明を行います。「社内規則上、そのような対応はできません」といった説明を繰り返し、相手に正当な理由を理解してもらう努力が必要です。
解決を急がず、不明な点は「わからない」と答える
カスハラに対する対応では、相手のペースに引きずられず、解決を急がないことが大切です。相手が焦って解決を迫ってくる場合でも、迅速な判断を避け、慎重に状況を分析する必要があります。不明な点がある場合には、無理に答えを出すのではなく、「現時点ではわかりかねますので、確認の上、改めてご連絡いたします」と答えることで、冷静な対応を示すことができます。
また、解決を急がない姿勢は、相手の要求が正当であるかどうかの見極めも有効です。相手が理不尽な要求を繰り返す場合、焦らずに時間を稼げば、冷静な判断を行う時間を確保できます。この過程では、社内の関係部署と連携し、最適な対応策の検討が重要です。
謝罪をするときは法的責任を認めない言い方にする
顧客対応において謝罪が必要な場合でも、言葉選びには注意が必要です。謝罪が法的責任を認めたと解釈されるケースがあるため、言葉遣いを慎重に選びましょう。たとえば、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」といった表現は、相手の感情を和らげつつ、法的責任を回避する適切な謝罪の例です。一方、「当社の過失です」といった表現は、責任を認めたと解釈される可能性があるため避けた方が無難です。
謝罪を行う際には、問題の具体的な原因や解決策に触れず、あくまで相手の感情に配慮した表現を用いましょう。このような対応は、相手の不満を軽減しつつ、企業としてのリスクを最小限に抑える効果があります。
相手の名前や住所、連絡先を確認する
カスハラ対応において、相手の名前や住所、連絡先の確認は重要なステップです。これにより、相手が特定され、トラブルがエスカレートした場合にも適切な対応が可能となります。特に、相手が匿名を希望する場合や虚偽の情報を提供する可能性がある場合には、慎重に情報収集を行う必要があるでしょう。この際、「確認のためにお伺いしております」といった丁寧な表現を用いて、相手に不信感を抱かせないよう配慮しましょう。
また、相手の情報を記録する際には、個人情報保護法に基づき適切な管理が求められます。相手に安心感を与えるためにも、収集した情報の取り扱いについて明確に説明し、信頼関係を築きましょう。
相手に諦めてもらう
カスハラ対応の最終的な目標は、相手に諦めてもらうことです。このプロセスでは、理不尽な要求に対して一貫した対応を行い、相手がこれ以上の要求を続けても意味がないと感じる状況を作り出します。たとえば、「これ以上の対応は致しかねます」といった言葉を繰り返し使用すれば、相手に対応の限界を理解してもらえるでしょう。
また、相手が感情的な場合でも、冷静さを保ち、毅然とした態度を示しましょう。このような対応を通じて、相手が自ら要求を引き下げる可能性を高められます。
必要であれば警察や弁護士と連携する
カスハラがエスカレートし、暴力や脅迫などの違法行為に発展した場合には、速やかに警察や弁護士との連携が必要です。このような場合、企業が独自に対応を続けることで事態がさらに悪化するリスクがあります。専門家の協力を得られれば、適切な法的対応を講じることが可能となり、スタッフや企業全体を守れるでしょう。
また、警察や弁護士との連携を検討する際には、被害の記録を詳細に残しておきます。具体的には、暴言や脅迫の内容、日時、状況などを記録し、必要に応じて証拠として提出できるよう準備しておきましょう。このような取り組みは、トラブル解決の迅速化に寄与するだけでなく、同様の問題が再発するリスクを減らす効果も期待できます。
カスハラ対策のポイント
ここでは、カスハラ対策のポイントをご紹介します。
普段から顧客と良好な関係を築いておく
カスハラを未然に防ぐためには、普段から顧客と良好な関係を築いておきましょう。日常的なコミュニケーションを通じて、顧客に信頼感や安心感を与えれば、不満やクレームがエスカレートする可能性を減らせます。
たとえば、迅速な対応や丁寧な言葉遣い、誠実な姿勢を見せれば、顧客との信頼関係の強化が可能です。顧客が企業に対して信頼を持っている場合、問題が発生しても感情的な行動に出るケースが少なくなる傾向があるとされています。
また、定期的なアンケートやフィードバックを通じて、顧客の意見を積極的な収集も効果的です。この取り組みにより、顧客が自分の声が企業に届いていると感じられれば、クレームが大きな問題に発展するリスクを低減できます。さらに、顧客からの意見や要望を積極的に取り入れる姿勢を見せれば、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
カスハラは許さないことを表明しておく
企業として、カスハラは許さないという姿勢を明確に示すことが重要です。顧客に対しても、このポリシーを周知すれば、無用なトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。具体的には、店舗やウェブサイトに「お客様との適切な関係を大切にしていますが、暴言や理不尽な要求には対応いたしかねます」といった注意書きを掲示すれば、顧客に対して企業のスタンスを明確に伝えられるでしょう。このような取り組みは、カスハラを抑止するだけでなく、スタッフを守る環境づくりにもつながります。
また、スタッフに対しても、カスハラを受けた場合には毅然とした態度を取るような教育が必要です。企業全体でカスハラに対抗する姿勢を共有し、一貫した対応を行えば、顧客が過剰な要求を諦める可能性が高まります。
カスハラ対応マニュアルを用意しておく
カスハラが発生した際に迅速かつ適切に対応するためには、事前にカスハラ対応マニュアルを用意しておくことをおすすめします。このマニュアルには、対応手順や具体的な言葉遣いの例、エスカレーションの基準などを明記しておき、スタッフが迷わず行動できる環境を整えましょう。
たとえば、カスハラの種類に応じた対応例をマニュアルに含めることが効果的です。感情的な顧客に対する対応方法や、理不尽な要求をかわす言葉遣いなど、実践的な内容を盛り込めば、スタッフが現場で活用しやすくなります。また、マニュアルには法律に基づいた対応策も記載しておくと、スタッフが法的なリスクを回避しつつ適切に対応できるようになるでしょう。
カスハラ対応の練習をしておく
実際にカスハラが発生した場合に備えて、対応の練習を日ごろから行うことが重要です。ロールプレイング形式でシミュレーションを行えば、スタッフは理論だけでなく実践的なスキルを身につけられるでしょう。この練習では、想定されるシナリオをいくつか用意し、スタッフがどのように対応するべきかを具体的に学びます。
たとえば、感情的な顧客への対応や、理不尽な要求をかわす方法、または謝罪の言葉選びの練習などを行いましょう。さらに、練習を通じて、スタッフが自分の対応に自信を持てば、現場でのストレスや不安を軽減できます。このような取り組みは、スタッフの精神的な負担を軽減するとともに、顧客対応の質を向上させる効果があるでしょう。
記録を残せる体制を整えておく
カスハラに関するトラブルが発生した場合には、詳細な記録を残しておくことが重要です。この記録は、後々のトラブル解決や法的対応において非常に役立ちます。具体的には、日時、場所、顧客の言動、対応内容などを正確に記録することが求められます。記録を残す際には、感情的な表現や主観的な意見を避け、事実のみの客観的な記載が重要です。
また、記録を残すための体制を整えるには、専用の記録システムやツールの導入がおすすめです。たとえば、顧客対応履歴をデジタルで管理できるシステムを利用すれば、情報の共有や分析が容易になるでしょう。このようなシステムは、トラブルの再発防止やスタッフ間の連携強化にも寄与します。
クレーム情報を共有できる体制を整えておく
カスハラに対応する際には、クレーム情報を迅速に共有できる体制の構築が重要です。スタッフ間で情報が共有されていない場合、同じ顧客からのクレームが繰り返される可能性があり、対応が不十分になる場合があります。そのため、クレーム情報を一元的に管理し、必要に応じて関連部門と情報を共有できる仕組みを整備することが求められます。
たとえば、クレーム管理システムを導入すれば、顧客の対応履歴や現在の進捗状況をリアルタイムで把握が可能になるでしょう。このようなシステムを活用すれば、スタッフが適切な対応を迅速に行えるようになり、顧客満足度の向上やカスハラのエスカレーション防止につながります。
さらに、共有された情報をもとに定期的な会議や研修を行い、スタッフが対応スキルを向上させる機会を設けるのもおすすめです。このような取り組みを通じて、企業全体でカスハラに対抗する体制を強化できます。
カスハラの事例
ここでは、具体的なカスハラの事例をご紹介します。
土下座を強要させた事例
土下座を強要する行為は、カスタマーハラスメント(カスハラ)の典型的な事例の一つとして広く知られています。このような行為は、スタッフに対する精神的な負担が非常に大きく、場合によっては法的な問題に発展するケースもあります。具体的なケースでは、店舗や企業のサービスに不満を持った顧客が、店員に対して土下座を要求し、その行為を実際にさせた事例が報告されています。このような状況に至る背景には、顧客が過度な権利意識を持ち、自分の要求が通らないことに対して感情的に反応する傾向が見られます。
たとえば、あるアパレルショップでの事例では、タオルケットに穴が空いていたことを理由に、顧客がスタッフに対して謝罪を超える要求を行いました。この顧客は周囲の他の客にも聞こえる声でスタッフを責め立て、その場の空気を支配する形で土下座を強要しました。しかし、こうした行為はスタッフの自尊心を著しく傷つけ、長期的な心理的トラウマを引き起こす可能性があります。また、土下座を強要された場合、場合によっては刑法の強要罪に該当する場合があり、企業やスタッフが被害者として訴訟を起こすことも可能な場合があります。
このような事態を防ぐためには、スタッフが土下座を要求された場合の具体的な対応策の事前教育が重要です。たとえば、毅然とした態度で「そのような行為は企業の規則上対応できません」と説明し、エスカレーションを行う手順を徹底が必要です。また、店舗や企業が、こうしたハラスメントに対して法的措置を取る意思を公にすることも、抑止力として効果的とされています。
店に居座り続けた事例
顧客が店舗に居座り続ける行為も、カスハラの深刻な例として挙げられます。この行為は、他の顧客やスタッフの業務に支障をきたし、営業活動を大きく妨害するものです。多くの場合、このような居座り行為は、顧客が自己の要求を強引に通そうとする中で発生します。特に感情的になった顧客が、問題解決に納得しないまま居座り続けるケースが典型的です。
ある飲食店での事例では、先に注文したにもかかわらず他の顧客に先に商品が届けられたとして、顧客がクレームを申し立てました。顧客は激怒し、店が退去を求めたあとも店内に居座り続けたと言います。その結果、不退去罪で現行犯逮捕されました。このような行為は、他の顧客に不快感を与えたり、スタッフが他の業務に集中できなくなったりするなど二次的な問題を引き起こします。
この種のカスハラに対処するには、まずスタッフが冷静かつ迅速に状況を把握し、適切な対応を取ることが重要です。具体的には、顧客の要求を記録し、上司や管理者に速やかなエスカレーションが必要です。また、警察への通報基準を事前に定めておくことで、深刻な事態に陥る前に迅速な対応が可能になります。加えて、店内に防犯カメラを設置し、顧客とのやり取りを記録し、あとのトラブル解決に役立つ証拠を確保することが推奨されます。このような対策を講じれば、企業は居座り行為による損害を最小限に抑えられるでしょう。
まとめ
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、企業やスタッフに深刻な影響を及ぼす問題であり、その予防と対応策がますます重要視されています。土下座の強要や店舗への居座りといった事例は、顧客の過剰な行動が業務妨害やスタッフの精神的負担につながる典型例です。これらの問題に対処するためには、企業として明確な対応方針を掲げ、スタッフに具体的なマニュアルや研修の提供が不可欠です。また、事前に顧客との良好な関係を築き、カスハラを許さない姿勢を示せば、問題の発生を抑制が可能です。さらに、記録の徹底や情報共有体制を整えれば、トラブル対応を迅速かつ適切に進められるでしょう。必要に応じて法的措置も視野に入れ、スタッフの安全と企業の信頼を守る取り組みが求められます。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。