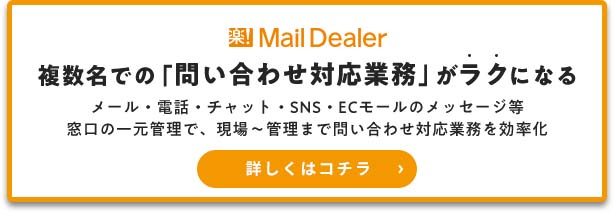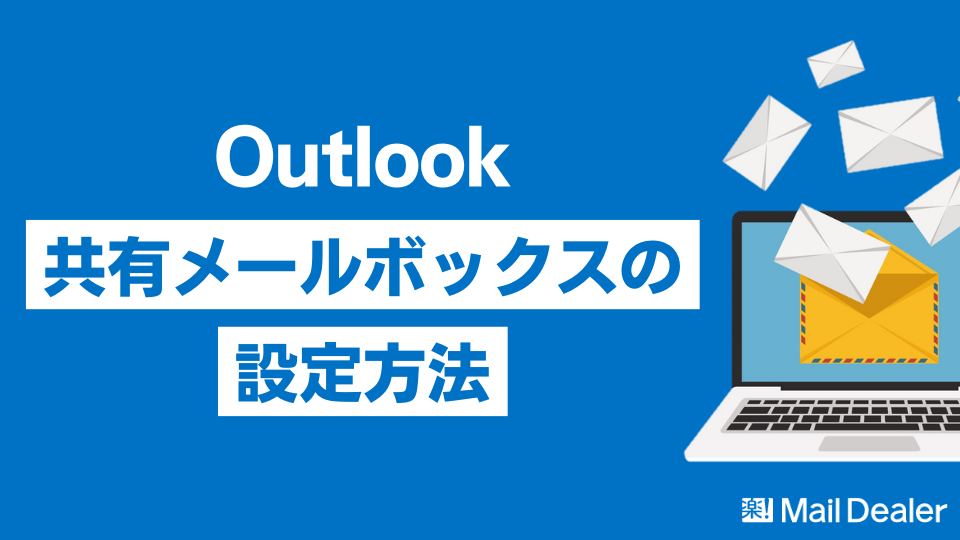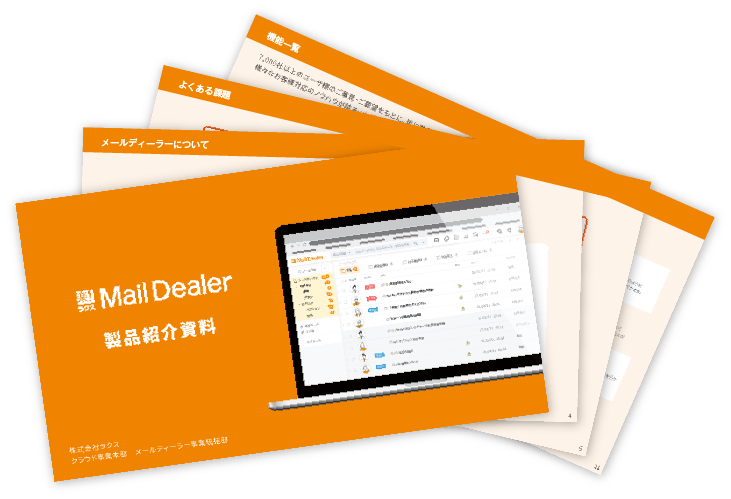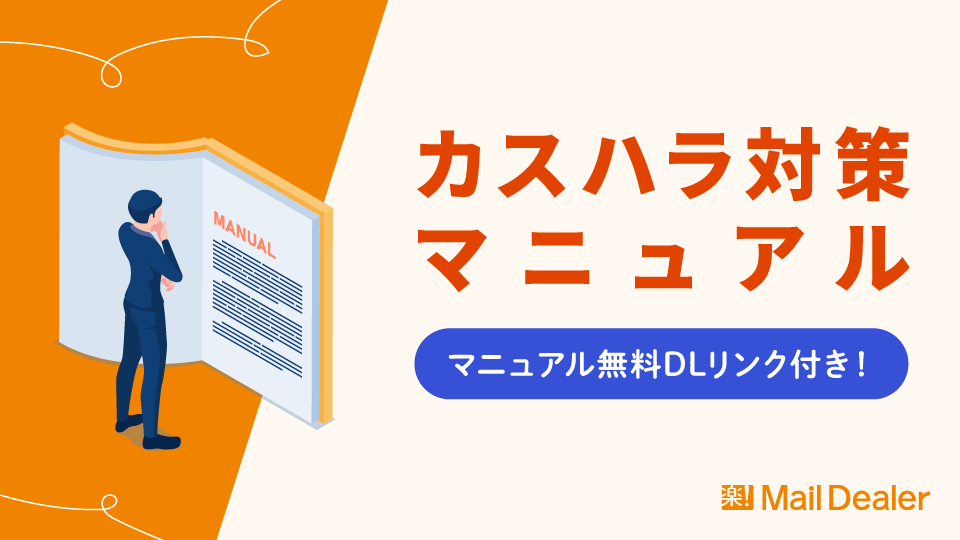
近年、企業の窓口や接客現場で「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」が深刻な問題となっています。企業に対する理不尽な要求や暴言、クレームにより、従業員が精神的な負担を抱えるケースが増加しています。
厚生労働省や東京都のマニュアルでは、企業が取るべき対応が示されており、適切な対策を行うことで従業員を守ることが求められています。本記事では、カスハラの定義から具体的な対策までをご紹介します。
カスハラとは
近年、「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」が大きな社会問題となっています。企業の窓口や店舗において、不当な要求や威圧的な言動が増加し、従業員が精神的に追い詰められるケースが後を絶ちません。
適切なクレーム対応は企業にとって重要ですが、カスハラはこれまでのクレームとは異なり、対応を誤ると企業と従業員に大きな精神的負担を抱えさせ、退職などに繋がるケースは少なくありません。そのため、企業にはカスハラの正しい理解と対策が必要不可欠です。
カスハラとクレームの違い
カスハラとクレームは混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。クレームは、顧客が商品やサービスに対して問題を指摘し、改善を求める行為です。一方、カスハラは不当な要求や過剰な言動が含まれ、企業や従業員に対して理不尽な負担を強いる行為です。
| クレーム | カスハラ | |
|---|---|---|
| 目的 | サービスの改善を求める | 威圧や攻撃が目的となる |
| 態度・言動 | 冷静な指摘 | 暴言や執拗な要求を繰り返す |
| 要求の内容 | サービスへの改善要望 | 過剰または不当な要求 |
| 対応の必要性 | 企業が真摯に対応する必要がある | 必要に応じて毅然とした対応が求められる |
カスハラに対して適切な対応を取らないと、従業員が精神的な負担を抱えるだけでなく、業務の効率低下や職場環境の悪化につながる可能性があります。
カスハラはなぜ増加しているのか
社会の変化や顧客の意識の変化や、企業への問い合わせ難易度の低下がカスハラ増加の後ろ押しになってしまっていると言われています。
-
SNSの影響
企業の対応がSNSで拡散されることにより、企業はクレームを慎重に扱わざるを得なくなっています。その結果、一部の顧客が「強くクレームを言えば特別な対応をしてもらえる」と考え、過剰な要求をするケースが増えています。 -
顧客第一主義の誤解
「お客様は神様です」という言葉が広く認知されていますが、本来の意味とは異なり、顧客が何をしても許されるという誤った考え方が根付いてしまいました。その結果、従業員に対して理不尽な要求をする顧客が増えているのです。
カスハラの具体例
カスハラにはさまざまな形態があり、業種や業態によって発生するケースが異なります。以下のような行為が見られた場合は、カスハラの可能性が高いと考えられます。
社会の変化や顧客の意識の変化や、企業への問い合わせ難易度の低下がカスハラ増加の後ろ押しになってしまっていると言われています。
-
威圧的な言動
店頭やコールセンターで大声を出し、従業員を威嚇する行為が該当します。暴言や人格否定を伴うケースも多く、従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を与えます。 -
過剰な要求
「他の店ではこうしてくれた」「上司を出せ」など、理不尽な特別対応を求める行為もカスハラの一種です。対応を誤ると、企業全体の業務が停滞する要因になります。 -
執拗なクレーム
企業が適切に対応した後でも、何度も同じ内容でクレームを繰り返す行為もカスハラとみなされる場合があります。対応に時間を取られ、本来の業務に支障をきたす恐れがあります。 -
個人攻撃
採用ホームページなどで紹介されている特定の従業員に対して名指しで批判を行い、時にはSNSなどを利用して誹謗中傷するケースもあります。従業員個人に大きな精神的ダメージを与え、企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼします。
カスハラ対策は必要?
企業にとって、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は避けて通れない課題となっています。近年、顧客による不当な要求や暴言、威圧的な行動が増加しており、対応を誤ると従業員のメンタルヘルスや企業の信頼に深刻な影響を与える可能性があるため、企業としてのカスハラ対策は必須です。
また、厚生労働省の指針により、企業には「従業員をカスハラから守る義務」があると明記されています。適切な対策を講じなければ、法的責任を問われるケースも今後は考えられるでしょう。
出典:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf
カスハラ対策と企業義務
カスハラ対策は、企業の選択ではなく「義務」となりつつあります。厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定し、企業が取るべき対応を示しています。
| 対策項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本方針の策定 | カスハラ対応の方針を社内外に明示する |
| 従業員の保護 | 従業員が被害を受けた際の相談窓口を設置する |
| マニュアル整備 | 適切な対応手順を社内で共有する |
| 研修の実施 | 従業員にカスハラ対応の研修を行う |
カスハラを放置するリスク
カスハラを放置すると、企業にはさまざまな悪影響が及びます。特に、従業員の離職や企業イメージの低下など、長期的なダメージにつながる可能性があります。
【カスハラを放置することで発生するリスク】
-
従業員の離職増加
カスハラを受け続けた従業員は、精神的な負担を抱え、最終的に離職する可能性が高まります。従業員が安心して働ける環境を整えることが、企業の安定運営にとって不可欠です。 -
企業の信頼低下
SNSの発達により、カスハラを放置する企業の対応はすぐに拡散されます。「従業員を守らない企業」と認識されると、顧客や求職者からの信頼を失うリスクが高まります。 -
業務効率の低下
従業員がカスハラ対応に時間を取られることで、本来の業務が滞ります。生産性の低下につながるだけでなく、他の顧客への対応にも影響を与える可能性があります。 -
法的責任の発生
企業には、従業員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」があります。カスハラを放置すると、企業がこの義務を果たしていないと判断され、労働基準法違反などの問題に発展する恐れがあります。
企業が参考にできるカスハラ対策マニュアル
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は、企業ごとに異なる対応が求められます。そのため、既に対策を講じている企業の発行している「カスハラ対策マニュアル」を参考にし、スピード感をもって対策を進めましょう。
厚生労働省や東京都などの公的機関が提供するマニュアルには、カスハラの定義や具体的な対策が記載されており、企業がすぐに導入できる内容も多く含まれています。これらを活用することで、効率的にカスハラ対策を進めることができます。
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル
厚生労働省においても、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しており、企業が取るべき具体的な対応を示しています。このマニュアルに記載されているポイントを下記にまとめてみました。
【厚生労働省マニュアルの主なポイント】
-
カスハラの定義
単なるクレームとカスハラの違いを明確にし、企業が対応すべきケースを判断しやすくすることが目的です。 -
企業の対応方針
カスハラ行為を断固として許さない方針を打ち出し、社内外に周知することで、従業員を守る姿勢を示します。 -
従業員の保護措置
被害に遭った従業員へのメンタルケアや相談窓口の設置など、適切なフォローアップ体制を整えることが求められます。 -
対応マニュアルの策定
カスハラが発生した際に、どのような手順で対応するかをあらかじめ決めておくことで、現場の混乱を防ぐことができます。
このマニュアルは、企業がカスハラ対策を進める際の基本的な指針となります。具体的な事例も記載されているため、実務に活かしやすい内容となっています。
また、メールディーラーも、「従業員の安全を守るために カスタマーハラスメント対応ガイド」を配布中ですので、是非ダウンロードしてみてください。
東京都の各団体共通マニュアル
東京都でも、企業や団体が共通して利用できる「カスハラ対策マニュアル(素案)」を作成しています。このマニュアルは、業種を問わず広く活用できる点が特徴です。
【東京都のマニュアルの特徴】
-
業種を問わない汎用性
飲食業、小売業、医療機関など、さまざまな業界で活用できるよう設計されています。業種ごとの違いを踏まえつつ、共通する基本的な対応策がまとめられています。 -
具体的な対応例
たとえば、レストランでの暴言、病院での執拗なクレーム、店舗での威圧行為など、現場で発生しやすい事例ごとに適切な対応方法が示されています。 -
法的視点の考慮
労働基準法や消費者保護法に基づいた説明があり、企業が法的トラブルを回避するためのポイントも記載されています。 -
組織内の対応強化
特定の従業員が一人で対応するのではなく、「複数人での対応を推奨」し、発生した事例を記録して共有することの重要性が強調されています。
企業が実施すべきカスハラ対策
カスタマーハラスメント(カスハラ)への適切な対応は、企業の信頼を守るだけでなく、従業員の安全と働きやすさを確保するためにも重要です。カスハラを放置すると、従業員の離職増加、企業の評判低下、業務の停滞といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、企業は体系的な対策を講じる必要があります。
ここでは、企業が具体的に実施すべきカスハラ対策を紹介していきます。
基本方針の策定
企業としてカスハラにどう向き合うのかを明確に示し、従業員と顧客の双方に周知することが求められます。
【基本方針に明記するべきこと】
- 何をカスハラと判断するかを明確にする
- カスハラに対する企業の姿勢を明確化する
- 対応の一貫性を保ち、従業員が判断に迷わないようにする
また、カスハラの対応マニュアルを周知し、従業員にカスハラに対する意識を持たせるということも重要です。
社内相談窓口の設置
従業員が安心して相談できる環境を整えることも重要です。カスハラの被害を受けた際に、すぐに報告できる仕組みを作ることで、問題の早期解決につながります。
| 問い合わせ形式 | 特徴 |
|---|---|
| 専用メールアドレス | 迅速な対応が可能で、記録も残る |
| 電話相談窓口 | 直接話せるため、緊急時の対応に適している |
| 第三者機関の活用 | 外部の専門機関に委託し、従業員が相談しやすい環境を提供 |
特に、中小企業では社内に適切な窓口を設置するのが難しい場合もあるため、外部機関を活用するのも有効な手段です。
マニュアルの作成
現場の従業員が適切に対応できるように、カスハラ対応をある程度マニュアル化することも必要でしょう。
| 記載すべき内容 | 内容 |
|---|---|
| カスハラの定義 | どのような行為がカスハラに該当するか明確にする |
| 初期対応の流れ | 暴言・威圧的な行為を受けた際の基本的な対応方法 |
| エスカレーション基準 | 現場対応が難しい場合に、上司や専門部署に報告する流れ |
| 法的対応の基準 | どのようなケースで警察や弁護士と連携するか |
カスハラが発生した際、従業員が「どのように対応すればいいのか」を判断できるような状態を作ることが重要です。
カスハラ対応研修の実施
研修を通じて、従業員が適切な対応スキルを身につけることが求められます。特に、冷静に対応するためのトレーニングが重要です。
| 研修内容 | 目的 |
|---|---|
| カスハラの定義と種類 | 正当なクレームとカスハラの違いを理解する |
| 初動対応の重要性 | 迅速で適切な対応を学び、状況悪化を防ぐ |
| 毅然とした対応の仕方 | 顧客に対して冷静かつ適切に対応する方法 |
| エスカレーションの基準 | 一人で抱え込まず、適切に上司へ報告する |
また、研修ではロールプレイを取り入れると効果的です。実際の場面を想定し、どのような対応が適切かを学ぶことで、現場での実践力が高まるでしょう。
事例やノウハウの蓄積
カスハラの対応経験を企業全体で共有し、ノウハウを蓄積することも重要です。
| 蓄積方法 | 内容 |
|---|---|
| 対応記録の作成 | 発生したカスハラ事例と対応結果を記録 |
| ケーススタディの作成 | 具体的な事例を分析し、研修に活用 |
| 社内データベースの構築 | 蓄積した事例を従業員が参照できる仕組みを作る |
特に、対応の良かった事例や改善すべき点を整理し、マニュアルや研修に反映させましょう。また、他社の事例を参考にするのも、より効果的な対策を講じるために役立ちます。業界団体や行政機関が提供する情報を活用し、企業ごとに適した対策を強化していくことが求められます。
カスハラが実際に発生した際の対応方法
カスタマーハラスメント(カスハラ)が発生した場合、企業は迅速かつ適切に対しなくてはいけません。対応が不適切な場合、被害を受けた従業員の負担が増し、企業の信用低下にもつながる可能性があります。
適切な対応の流れを確立し、「ヒアリング→事実確認→判断→顧客対応→アフターフォロー」のプロセスを徹底することが重要です。
ヒアリング
カスハラが発生した際、まずは被害を受けた従業員から状況を詳しく聞き取ることが重要です。従業員が冷静さを失っている場合もあるため、上司や担当部署が適切にサポートしながら進めます。
【ヒアリングシートの一例】
| ヒアリング項目 | 記入内容の例 |
|---|---|
| 発生日時 | 〇月〇日15:30頃 |
| 発生場所 | 店舗内レジカウンター |
| 顧客の特徴 | 40代男性、スーツ姿 |
| 問題行動 | 大声での威圧、長時間の苦情 |
| 対応経緯 | 他の従業員が対応するも収まらず、責任者が対応 |
記録を残すことで、後の対応がスムーズになり、企業としての判断材料になるでしょう。
事実確認
ヒアリング後、客観的な事実を確認することが必要です。一方的な判断を避け、証拠をもとに公平な対応を行うことが求められます。
事実確認に活用できる証拠
| 証拠 | 活用方法 |
|---|---|
| 防犯カメラ映像 | 顧客の行動や発言を確認 |
| 音声録音 | 威圧的な言動の有無を判断 |
| 目撃証言 | 他の従業員や顧客の証言を収集 |
| メールやチャットの記録 | 文面でのハラスメント行為を確認 |
たとえば、顧客から「従業員の対応が悪い」と指摘された場合、カメラ映像を確認し、実際の接客態度を確認することで、誤解や事実誤認を防げるでしょう。
カスハラか正当なクレームかの判断
事実確認の結果、顧客の行為がカスハラに該当するのか、正当なクレームなのかを判断します。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 正当なクレーム | 商品の不良、接客ミスに関する指摘 |
| 厳しい意見 | 言葉遣いや態度への不満 |
| カスハラ | 長時間のクレーム、威圧的な言動、人格否定 |
特に、顧客が威圧的な態度をとったり、不当な要求を続けたりする場合はカスハラと判断し、毅然とした対応が必要です。
顧客への対応
カスハラと判断した場合、感情的にならず冷静に対応することが重要です。
基本的に、カスハラへの対策においては、毅然とした態度で対応し、必要以上に謝罪をしないことが有効とされています。また、同じ要望を繰り返す顧客に対しては、一貫して「対応できない」と明言するなど、対応に一貫性を持たせることも重要です。
【具体的な対応例】
| 状況 | 対応フレーズ例 |
|---|---|
| 長時間のクレーム | 「これ以上の対応はできませんので、ご理解ください」 |
| 過剰な謝罪要求 | 「すでにお伝えした対応が最善です」 |
| 暴言・威圧的な態度 | 「冷静にお話しいただけない場合、対応を終了します」 |
万が一、顧客がエスカレートし暴力や脅迫に及ぶ場合は、即座に警察へ通報する判断が必要です。企業としての対応ルールを明確にし、従業員が安心して対応できる環境を整えましょう。
カスハラに対応した従業員へのアフターフォロー
カスハラに対応した従業員の精神的負担を軽減するため、適切なフォローを行うことが重要です。アフターフォローの方法は、
- 上司や同僚が話を聞き、精神的なケアを行う
- 必要に応じて専門のカウンセリングを受けられる体制を作る
など様々です。フォロー体制は複数用意しておき、従業員のシチュエーションに応じてフォローができる体制を整えましょう。
従業員が安心して働ける環境を作ることで、離職防止や職場の士気向上にもつながります。
カスハラ対策は事前対策が最も重要!
カスハラ対策を効果的に行うためには、状況を正確に把握し、情報をチーム全体で共有することが極めて重要です。企業の管理職は、自社ではカスハラが発生していないと考えることが多いですが、実際には従業員がカスハラを認識できていない場合や、報告が上がっていない場合が少なくありません。これにより、カスハラが見過ごされることが頻繁に発生してしまい、見えないところで従業員の精神に悪影響を与えているケースは少なくありません。
そのため、カスハラとは何かをしっかりと定め、対策を講じることで従業員を守りましょう。
情報共有の重要性
情報を適切に共有することで、カスハラの発生を早期に把握し、迅速かつ適切な対応が可能になります。電話やメールなどの問い合わせ窓口でのやりとりでは、すべての情報が管理職や関係者に届けられるわけではないため、基本的に顧客からの問い合わせに関するやり取りは、オープンな環境で行うことをおすすめします。
電話問い合わせの管理
顧客からの問い合わせを録音することで、後から内容を確認することができるでしょう。また、録音データを自動で文字起こしするシステムを導入すれば、対応内容を簡単に確認でき、カスハラの実態を把握することも可能になります。
これにより、複数の従業員が迅速に内容を確認し、連携を図ることができるため、早期の対応が可能です。
メールでの問い合わせ管理
メールの問い合わせも重要な情報源ですが、個々の従業員が対応した内容を他の従業員が把握できていないことがあります。これを解消するために、共有メールアドレスやメール共有システムを導入し、全員がリアルタイムで情報にアクセスできるようにすることが大切です。
これにより、従業員の間で情報の食い違いや、カスハラの見逃しを防ぐことができます。また、担当以外の従業員がカスハラに気づき対応を促すことによって、的確な対応をすることも可能になるため、メールでのやり取りの見える化は非常に重要です。
株式会社ラクスでは、複数人のメール業務をサポートする、メール共有管理システム「メールディーラー」を提供しています。複数人でメールでの問い合わせ対応業務の効率化を検討する際には、是非お問い合わせください。
まとめ
適切なカスハラ対策を行うためには、日ごろからカスハラの発生に備えた体制づくりが必要です。厚生労働省や東京都が作成した「指針やマニュアル」を活用しながら、相談窓口の設置や研修の実施などさまざまな対策を行いましょう。
また、カスハラは発生してからの情報共有も重要です。問い合わせ管理やメール共有システムを活用しながら情報を共有し、対策に役立てましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。