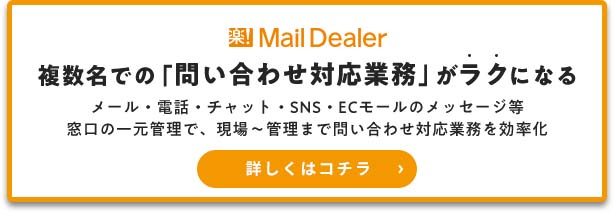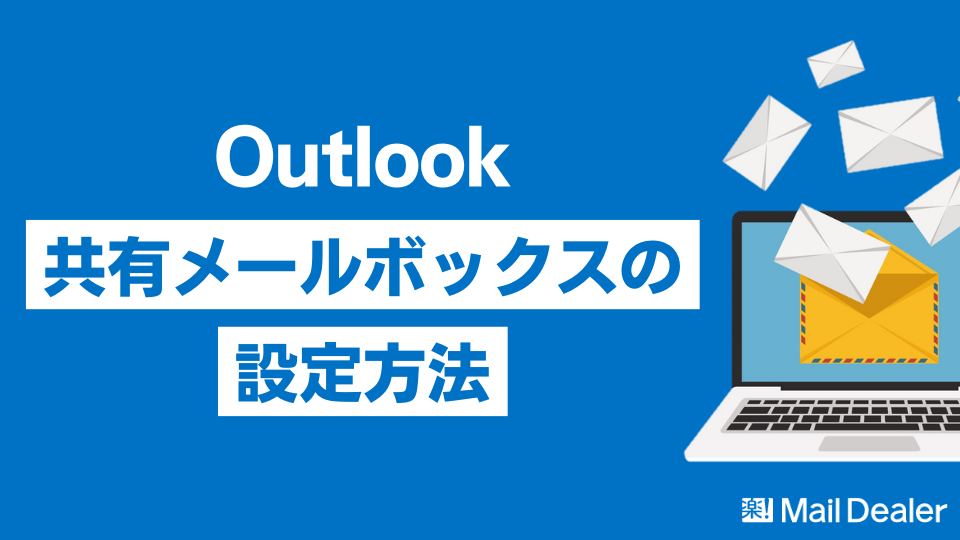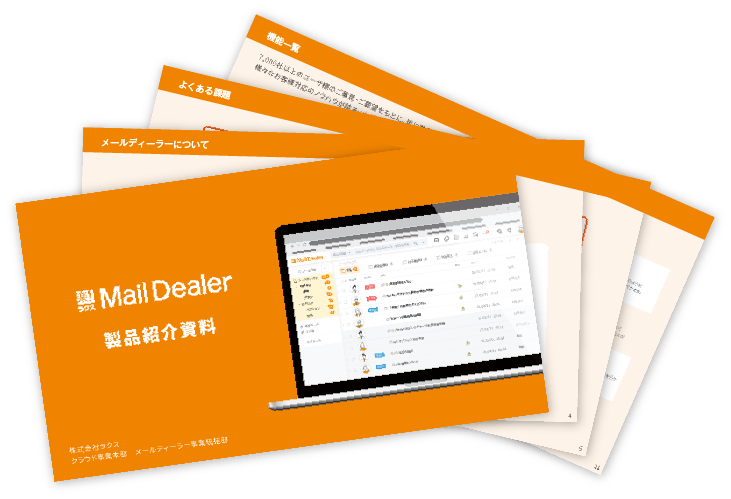2024年10月4日、東京都は「カスタマーハラスメント防止条例」(以下、カスハラ防止条例)を制定し、2025年4月1日から施行されます。この条例は、顧客からの不当な要求や迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)を防止し、就業者の就業環境を守ることを目的としています。全国初の包括的なカスハラ防止条例であり、他の自治体にも影響を与える可能性が高いと注目されています。
本記事では、東京都カスハラ防止条例の概要や施行日、内容についてご紹介します。
カスハラとは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからの著しい迷惑行為を指します。具体的には、過剰な要求や不当なクレーム、暴言や脅迫などが含まれます。これらの行為は、就業者の精神的・肉体的負担を増大させ、職場環境の悪化や離職の原因となることが指摘されているのです。
カスハラの内容としては、以下のようなものが報告されています。
- 不当・悪質なクレーム
- 過剰なサービスの要求
- 暴言や脅迫
- 長時間にわたる拘束
これらの行為は、就業者の健康や職場の士気に悪影響を及ぼし、企業の業務効率や顧客満足度の低下にもつながるため、早急な対策が求められています。
カスハラに関連する法規制の現状
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、近年大きな社会問題となっていますが、現時点では明確にカスハラを取り締まる法律は存在しません。しかし、いくつかの既存の法律により、カスハラの一部行為が規制されています。ここでは、現行の法規制について整理します。
| 法律名 | 該当するカスハラ行為 | 具体的な規定 |
|---|---|---|
| 刑法 | 暴行・脅迫・名誉毀損 | 第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)、第230条(名誉毀損罪)など |
| 軽犯罪法 | 迷惑行為・業務妨害 | 第1条(公共の平穏を害する行為の禁止) |
| 労働基準法 | 就業者の安全・健康の確保 | 第5条(強制労働の禁止)、第89条(就業規則の義務付け) |
| 労働契約法 | 労働環境の整備 | 第5条(安全配慮義務) |
| 民法 | 損害賠償請求 | 第709条(不法行為に基づく損害賠償) |
刑法の適用
刑法では、顧客が就業者に対して暴力を振るった場合、暴行罪(刑法第208条)が適用される可能性があります。また、脅迫行為があった場合は脅迫罪(刑法第222条)に該当し、名誉を傷つける発言をした場合は名誉毀損罪(刑法第230条)が成立することがあります。これらの行為が認められれば、刑事罰が科される可能性があります。
軽犯罪法の適用
顧客が長時間にわたり店員に付きまとったり、大声で怒鳴り続けたりするなどの行為は、軽犯罪法(第1条)に違反する可能性があります。また、悪質なクレームによる業務妨害が認められれば、威力業務妨害罪(刑法第234条)が適用されることもあります。
労働関係法規による対策
労働基準法や労働契約法では、事業者に対し、就業者の安全と健康を確保する義務を課しています。特に、労働契約法第5条の安全配慮義務は、企業がカスハラのリスクを軽減するために適切な措置を講じる必要があることを示しています。
なお、厚生労働省は2022年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業に対し具体的な対策を提示しました。これにより、企業がカスハラ対策を講じる際の指針が示されました。
出典:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001104928.pdf
また、株式会社ラクスでのメール共有管理システム「メールディーラー」でも、「従業員の安全を守るために カスタマーハラスメント対応ガイド」を配布中ですので、是非ダウンロードしてみてください。
民法による損害賠償請求
顧客のカスハラ行為が、就業者や企業に経済的損失を与えた場合、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能となります。たとえば、理不尽なクレームによって企業が過度なコストを負担した場合、損害賠償を求めることができます。
現行法の限界と今後の課題
現行の法律では、一部の悪質なカスハラ行為に対して罰則を適用できますが、カスハラ全体を包括的に防止する法制度は整っていません。そのため、東京都のカスハラ防止条例のような新たな規制の整備が重要視されています。
東京都のカスハラ防止条例とは
東京都は、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防止するための条例を2024年10月4日に制定し、2025年4月1日から施行することを決定しました。全国で初めて都道府県レベルで制定されたこの条例は、就業者の就業環境を守り、顧客と事業者の健全な関係を促進することを目的としています。
条例制定の背景
カスハラは、就業者に精神的・肉体的負担を与え、企業のサービス品質や業務効率にも影響を及ぼします。東京都はこうした問題の深刻化を受け、「公労使による『新しい東京』実現会議」を通じて、カスハラ対策の必要性を議論しました。
その後、2023年10月31日には「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を設置し、条例制定に向けた具体的な議論を開始しました。そして、各業界団体や専門家の意見を踏まえ、2024年10月に正式に条例が成立したのです。
東京都カスハラ防止条例の目的
この条例の主な目的は以下の通りです。
| 目的 | 概要 |
|---|---|
| 就業者の保護 | カスハラから就業者を守り、安心して働ける環境を整備する |
| 事業者の責務明確化 | 企業が適切なカスハラ対策を講じることを促す |
| 都民への理解促進 | 顧客側にも適切な行動を求め、社会全体でのカスハラ抑制を目指す |
この条例により、企業は就業者をカスハラから守る義務を負い、東京都は防止対策を支援する役割を担います。
条例の適用対象
東京都カスハラ防止条例は、都内の全ての事業者、就業者、顧客を対象としています。
| 適用対象者 | 具体例 |
|---|---|
| 事業者 | 東京都内で営業する企業・店舗・事務所 |
| 就業者 | 都内で仕事をする全ての個人 |
| 顧客・取引先 | 企業のサービスを受ける一般顧客や取引先企業 |
この条例は、特定の業種や業態を限定せず、都内で事業を行う全ての企業・個人事業主に適用される点が特徴です。
今後の展開
東京都のカスハラ防止条例は全国で初の試みであり、他の自治体にも影響を与える可能性があります。今後、条例の具体的な運用方法や効果を検証しながら、さらなる規制強化が議論されることが予想されます。
関連記事:カスハラ対策マニュアル|マニュアル無料DLリンク付き!
東京都カスハラ防止条例の基本的な考え方
東京都カスハラ防止条例は、就業者の安全を確保し、事業者と顧客の適切な関係を維持することを目的としています。本条例の基本的な考え方は、単なる規制ではなく、社会全体でカスハラを防止し、適切な対応を促進する点にあります。この考え方は、以下の3つの要素を軸に構成されているとされています。
- カスハラを社会問題として認識し、都民全体で防止する
- 就業者が安心して働ける環境を確保する
- 事業者に適切な対応を求め、都と連携して防止策を推進する
カスハラは社会全体で防止すべき問題
東京都は、カスハラを単なる個別のトラブルではなく、社会全体で取り組むべき課題と位置づけています。
カスハラの影響は広範囲
カスハラは、直接被害を受ける就業者だけでなく、企業の経営やサービスの質にも悪影響を及ぼします。たとえば、過度なクレーム対応により就業者が疲弊すれば、サービスの低下や人材流出につながる可能性があります。
都民の意識改革が必要
企業側の対策だけでは限界があるため、顧客側の意識改革も不可欠です。本条例では、都民に対して「適切なクレーム対応の在り方」を周知し、過度な要求や威圧的な行為が許されないことを啓発していく方針を示しています。
就業者が安心して働ける環境を確保
本条例の大きな柱の一つが、就業者の保護です。東京都は、就業者が不当なハラスメントを受けずに働ける環境を整備することが重要であると考えています。
| 施策 | 概要 |
|---|---|
| カスハラ対応マニュアルの整備 | 企業に対し、就業者が適切に対処できるようマニュアル作成を推奨 |
| 相談窓口の設置 | 就業者がカスハラ被害を報告しやすい環境を整備 |
| 精神的・身体的ケアの強化 | カスハラ被害に遭った就業者に対し、医療機関やカウンセリングの支援を検討 |
これにより、就業者が不当な対応を強いられず、精神的負担を軽減できる環境の整備を目指します。
事業者と行政の連携による防止策の推進
条例では、企業にカスハラ防止の責務を負わせるだけでなく、東京都と連携して対策を推進することを求めています。
企業は以下の対策を講じることが求められます。
| 事業者が行うべき対策 | 具体例 |
|---|---|
| 社内ルールの整備 | カスハラに対する対応方針を明確にし、就業者へ周知 |
| 就業者研修の実施 | カスハラへの適切な対処法を教育 |
| 被害者の保護措置 | カスハラ被害を受けた就業者のケアや異動措置 |
東京都カスハラ防止条例の内容
東京都カスハラ防止条例は、顧客や取引先からの不当な要求や暴言などによるカスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐための規定を定めています。本条例は、事業者・就業者・顧客・行政の役割を明確にし、社会全体でカスハラを防止する仕組みを構築することを目的としています。
カスハラの定義
本条例において、カスハラは次のように定義されています。
「顧客等からのクレーム・言動のうち、要求の内容や手段が社会通念上不相当であり、就業者の就業環境を害するもの」
具体的なカスハラの例として、以下のようなものが挙げられます。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 暴言・侮辱 | 大声で怒鳴る、人格を否定する発言 |
| 身体的暴力 | 物を投げる、押す・叩くなどの直接的な暴行 |
| 執拗な要求 | 本来必要のない対応を何度も要求 |
| 威圧・脅迫 | SNSや口コミサイトでの悪評拡散をほのめかす |
| 不適切な長時間拘束 | クレーム対応による異常な長時間の拘束 |
カスハラ防止に関する基本理念
本条例は、カスハラを防止するために、就業者・事業者・顧客・行政が協力し、適切な関係を築くことを基本理念としています。
【基本理念の抜粋】
- 就業者の尊厳の保護
- 就業者が不当なハラスメントを受けず、安全に働ける環境を確保する。
- 顧客・事業者の適切な関係の構築
- 事業者は顧客対応の基準を設け、合理的な対応を実施する。
- 顧客も適切な要求や態度を心がける必要がある。
- 社会全体での意識改革
- 都民全体に対して、カスハラが許されないという認識を広める。
カスハラの一律禁止
本条例では、全ての事業者および顧客に対し「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と、カスハラを禁止しています。
カスハラ行為に対する一律禁止の規定は、就業者が顧客から不当な要求や暴力を受けることなく、健全な職場環境で働けるようにするために設けられています。企業は就業者を守る責任があり、カスハラの兆候を早期に察知して防止策を講じる必要があります。
就業者には支援体制を整備し、発生した場合には速やかな対応が求められます。また、顧客にも適切な行動を促すため、指導を行うことが重要です。
適用上の注意
カスハラ防止条例は、全ての事業者に適用されますが、その内容は企業の規模や業種によって異なります。大企業では、カスハラ防止策の詳細な策定や、研修などが求められる一方で、中小企業においては簡易な対応策や手続きが可能となる場合もあります。事業者は自身の規模や業種に応じた適切な対策を講じ、法令に則った実施を行わなければなりません。
また、顧客の要求やクレームが正当なものであるのに、カスハラだと不当に非難したり拒否したりすることは認められていません。
カスハラ防止に関する都・顧客・就業者・事業者の責務
この条例は、東京都、顧客、就業者、そして事業者が協力してカスハラの防止に取り組むことを求めています。それぞれの責務は以下のように定められています。
| 関係者 | 責務 |
|---|---|
| 東京都 | カスハラ防止策の推進・啓発 |
| 顧客 | 適切な対応を心がける |
| 就業者 | 企業のルールに従い、適切な対応を行う |
| 事業者 | カスハラ対策の整備・実施 |
カスハラ防止に関する都と区市町村の連携
東京都は、各区市町村と連携し、以下の取り組みを推進しています。
- 地域ごとのカスハラ防止対策の強化
- 相談窓口の整備と情報共有
- カスハラ発生時の迅速な対応支援
東京都と区市町村は、カスハラ防止に向けて緊密に連携し、地域ごとの特性を反映させた対策を講じるとしています。これにより、地域ごとの問題に対応するため、迅速かつ効果的な施策が進めることができるでしょう。
地域間で情報を共有し、共同でカスハラ防止のための活動を行うことにより、全体としてカスハラの発生を防ぐための体制が強化されるでしょう。
カスハラ防止指針の作成・公表
東京都は、事業者が適切な対応を取れるように「カスハラ防止指針」を作成・公表します。条例の11条1項・3項で定められています。また、同条2項で以下の事項が定められています。
- カスハラの内容に関する事項
- 都の施策に関する事項
- 事業者の取組みに関する事項
- 上記の他、カスハラを防止するための事項
カスハラ防止指針に基づく施策の推進・財政上の措置
本条例では、施策の実施にあたり、財政的支援も行うことが明記されています。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| カスハラ対策研修の実施 | 事業者向け研修やセミナーの開催 |
| 相談窓口の設置 | 就業者・企業向けの相談窓口を拡充 |
| 財政支援 | 中小企業向けに対策費用の補助を検討 |
このような支援を通じて、東京都はカスハラ防止対策を実効性のある取組みとなるよう進めています。
東京都カスハラ防止条例に対して企業が行うべきこと
「カスタマーハラスメント防止条例」によって、企業は就業者を保護し、顧客からの過度な要求や不当なクレームに適切に対応することが求められます。この条例は、就業者の精神的負担を減らすことを目的としており、企業は法的な責任を果たす必要があります。
まず、企業は自社で発生する可能性のあるカスハラ(顧客による過剰な要求や言動)を認識し、事前に防止策を講じることが求められます。就業者向けの研修や、顧客に対する適切な対応方法を定めたマニュアルの作成が重要です。また、カスハラが発生した場合、迅速な対応を取ることが企業の責務となります。
条例に基づく責任として、企業はカスハラを防止するために「努力義務」を負います。これは、事業者が自身の業務においてカスハラが発生しないよう配慮することを意味します。また、顧客との接点で問題が生じた場合、事業者は即座に対処し、就業者を守るための措置を講じなければなりません。
企業がこの規制を遵守しない場合、社会的信頼の低下や法的リスクが発生する可能性があるため、早期に適切な対応を行うことが企業の利益にもつながります。
まとめ
東京都は2025年に施行される「カスタマーハラスメント防止条例」を通じて、顧客からの不当な要求や暴言から就業者を守ることを目的としています。この条例では、カスハラの定義を明確にし、一律に禁止することを規定しました。また、就業者の尊厳と安全を守る基本理念を掲げ、事業者や顧客の責務も明示されています。
この条例を通じて、東京都と区市町村が連携して防止策を講じ、指針を策定・公表し、実効性のある施策を推進しています。これにより、社会全体でカスハラのない職場環境が整備されることが期待されるでしょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。