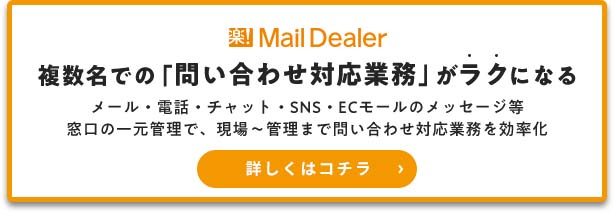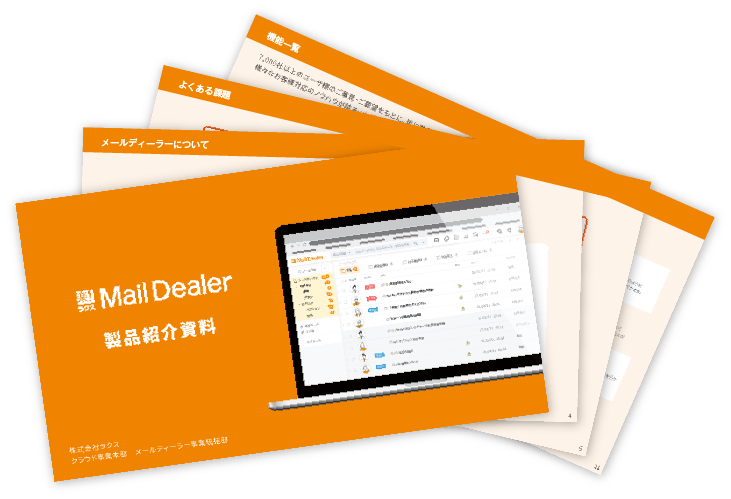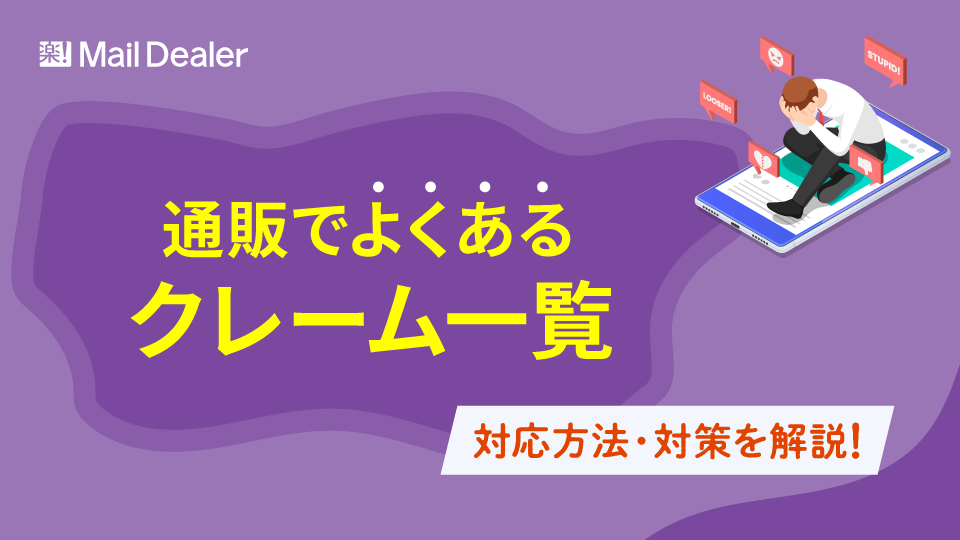
インターネット通販は便利な一方で、顧客との直接的なやり取りが少ないため、クレームが発生しやすい環境でもあります。商品が届かない、違う商品が届いた、返金がされないといった問題は、顧客にとっては大きなストレスになり、製品・サービスへの信頼度低下に直結します。
本記事では、通販でよくあるクレームとその対応・対策について解説し、適切なクレーム対応のポイントや避けるべきNG行動をご紹介します。
通販でよくあるクレームと対応・対策
通販サイトの運営では、クレーム対応が避けられません。しかし、適切な対応を行えば、顧客満足度を高め、リピーター獲得につなげることも可能です。ここでは、通販で発生しやすいクレームの具体例と、その対応策についてご紹介します。
欠品に関するクレーム
「注文したのに、後から在庫切れと言われた。どうなっているのか?」
「在庫管理がずさんで、信頼できない」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 在庫管理の強化 | 在庫システムを導入し、リアルタイムで更新する。 |
| 事前通知の徹底 | 在庫数が少なくなった時点で「残りわずか」の表示を行う。 |
| 代替案の提示 | 同等の商品を提案し、納得してもらう。 |
「申し訳ございません。現在、在庫切れとなっております」と謝罪し、代替品や再入荷時期をすぐに伝えましょう。顧客に「待つか、キャンセルするか」を選択してもらうと、納得感が高まります。この場合、顧客に選択を促すということが重要です。
商品配送の遅延に関するクレーム
【よくあるクレーム事例】
「発送予定日を過ぎても届かない」
「遅延の連絡がなく、不安になった」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 配送状況の見える化 | 追跡番号を通知し、進捗を確認できるようにする。 |
| 遅延時の迅速な連絡 | 配送遅延が発生した場合は、すぐにメールで案内する。 |
| 代替案の提示 | 急ぎの場合、別の配送方法を提案する。 |
まず、「配送遅延によりご迷惑をおかけし、申し訳ございません」と丁寧に伝えましょう。また、「いつまでに届くのか」を明確にすることで、顧客が不安から複数回問い合わせを行うような状況を防ぎ、対応工数の削減にも繋がります。
商品の破損・汚損・欠陥に関するクレーム
「届いた商品が壊れていた。交換できるのか?」
「開封したら汚れていた。新品なのか?」
「破損商品をお届けし、申し訳ございません」と誠意を持って謝罪し、「すぐに代替品をお送りします」と、迅速な対応を心がけましょう。
違う商品が届いたことに関するクレーム
【よくあるクレーム事例】
「注文したものと違う商品が届いた」
「サイズ違いが届いて困っている」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 発送時のダブルチェック | 商品ピッキング時と梱包時に、複数人で確認する。 |
| スムーズな交換手続き | 正しい商品を即日発送し、誤配送の商品は着払いで回収する。 |
| システムの見直し | 商品バーコードを活用し、人的ミスを減らす。 |
謝罪し、「正しい商品をすぐに発送します」と伝えます。交換手続きを簡単にし、顧客の負担を減らすことが重要です。
返金処理、返品に関するクレーム
【よくあるクレーム事例】
「返品したのに返金されない」
「手続きが複雑すぎてわかりにくい」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 返金処理の迅速化 | 返品受領後、速やかに返金手続きを行う。 |
| 返金ルールの明確化 | 返金までの期間を事前に明記し、顧客に理解してもらう。 |
| 自動化システムの導入 | 返金手続きをシステム化し、処理を迅速化する。 |
「返金が遅れており、申し訳ございません」と謝罪し、「○日以内に返金予定です」と具体的な日数を伝え、顧客の不安を少しでも払拭することに努めましょう。
電話やメールでのしつこいクレーム
【よくあるクレーム事例】
「何度も問い合わせているのに、回答がバラバラで混乱している」
「回答に納得できない」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| FAQの充実 | よくある質問をサイトに掲載し、問い合わせを減らす。 |
| 一貫した対応 | 社内で情報を共有し、どのスタッフが対応しても同じ説明ができるようにする。 |
| 対応方針の明確化 | 度重なる不当な要求には、適切な範囲での対応を提示する。 |
顧客が納得できるよう、「前回の対応と同じ説明を繰り返し行う」ことが重要です。また、「必要以上に対応しすぎない」ことで、長期的なトラブルを防げるでしょう。
通販のクレーム対応のポイント
通販ビジネスでは、クレーム対応の質が企業の信頼を左右します。適切な対応を行うことで、クレームをトラブルで終わらせるのではなく、顧客満足度向上の機会へと変えることが可能です。ここでは、通販のクレーム対応で特に重要なポイントをご紹介します。
まずは謝罪で相手に落ち着いてもらう
クレーム対応の第一歩は、「謝罪」です。顧客は商品やサービスに対して不満を持っているため、最初にしっかりと謝罪をすることで、感情を落ち着かせられるでしょう。
【適切な謝罪の例】
「ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。」
「ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。」
【避けるべき謝罪のNG例】
「弊社の責任ではありませんが…」
→言い訳がましく聞こえてしまう
「申し訳ないですが、こういうことはよくあります」
→顧客の不満を増幅させてしまう
謝罪の際には、顧客の気持ちを尊重する姿勢を示すことが重要です。原因が判明していなくても、まずは謝罪を述べることでクレームが悪化するのを防ぎます。
状況と事実を確認する
謝罪の後は、クレームの内容を正確に把握する必要があります。感情的に対応するのではなく、冷静に事実を整理し、解決策を提示できるようにしましょう。
| 内容 | |
|---|---|
| 1.クレームの詳細を聞く | 「いつ・どこで・何が起きたのか」を確認する。 |
| 2.注文情報をチェック | 購入履歴・配送状況・商品情報を確認する。 |
| 3.事実関係を整理 | 顧客の言い分とデータを照らし合わせ、対応方針を決める。 |
【質問例】
- 「お届けした商品に不具合があったとのことですが、どのような状態でしたか?」
- 「注文時のメールをお持ちでしたら、ご確認いただけますでしょうか?」
クレームの背景を丁寧に聞き取り、感情的にならず冷静に対応しましょう。顧客の話を最後まで聞くことで、不満を和らげる効果もあります。
余計なことを言わない
クレーム対応では、不必要な発言を控えることが重要です。曖昧な説明や無責任な発言が、さらに大きなクレームを招くことがあります。
言ってはいけないNGワード
| NGワード | 理由 |
|---|---|
| 「多分」「おそらく」 | 不確かな情報は信頼を失う原因になる。 |
| 「担当者が不在なので対応できません」 | 顧客の不信感を招く。 |
| 「当社では対応できません」 | 解決策を提示せずに断ると、さらなるクレームにつながる。 |
【適切な対応例】
「現在、状況を確認しております。確認が取れ次第、ご連絡いたします。」
「至急、担当者に確認し、折り返しご連絡いたします。」
無責任な発言は避け、「確認中」「対応中」など前向きな表現を使いましょう。顧客にとって必要な情報のみを簡潔に伝え、誤解を招かないようにすることが大切です。
電話よりメールで対応する
クレーム対応は電話よりもメールで行うほうがスムーズに進む場合が多いとされています。
メールは電話と比較して、聞き漏らしなどの発生リスクが低く、何を聞くかさえ予め定めておけば対応歴が浅いメンバーでもきっちりと顧客の状況を把握することが可能です。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 記録が残る | やり取りを後から確認でき、言った・言わないのトラブルを防げる。 |
| 冷静に対応できる | 文章で整理して伝えられるため、感情的な対応を避けられる。 |
| 時間をかけて適切な回答ができる | その場で焦って返答する必要がなく、正確な情報を伝えられる。 |
【適切なメールの書き方】
-
件名を明確にする
「【重要】返品対応について」 -
簡潔かつ丁寧な文章
「このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ございません。返品対応の詳細をご案内いたします」 -
具体的な対応策を提示する
「〇〇日までにご返送いただければ、交換品を発送いたします」
電話対応が必要な場合でも、内容をあとでメールで送ることで記録を残しましょう。特に感情的になりがちなクレームは、文章で冷静にやり取りするほうがスムーズに進みます。
やり取りを記録に残す
クレーム対応では、すべてのやり取りを記録に残すことが大切です。記録を残すことで、同じクレームが発生した際に迅速な対応ができるほか、社内での情報共有にも役立ちます。
記録に残すべき情報
| 記録項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| クレームの発生日時 | いつクレームが発生したのか。 |
| 顧客の氏名連絡先 | だれからのクレームか。 |
| クレームの詳細 | どのような内容のクレームか。 |
| 対応履歴 | どのように対応したか。 |
【記録を残すメリット】
-
一貫性のある対応ができる
過去の履歴を確認し、適切な対応が可能。 -
社内で共有しやすい
他のスタッフが対応する場合でも、スムーズに引き継げる。 -
法的トラブルを防げる
万が一トラブルに発展した際、証拠として活用できる。
電話対応後でも、必ず対応内容を記録し、必要に応じて上司や他部署と共有しましょう。メールでのやり取りを保存し、過去のクレームを分析することで、再発防止策をより具体的に設計することが可能になります。
通販のクレーム対応でやってはいけないこと
通販ビジネスでは、クレーム対応の仕方によって顧客の信頼が大きく変わります。適切に対応すれば信頼関係の強化につながりますが、間違った対応をすると企業の評価を下げる原因になります。ここでは、クレーム対応で絶対に避けるべき行動についてご紹介します。
NGワードを使う
クレーム対応の場では、顧客の感情を逆なでする言葉を使わないことが重要です。不用意な発言がさらなるトラブルを招くこともあるため、慎重な言葉選びを心がけましょう。
避けるべきNGワードとその理由
| NGワード | 理由 |
|---|---|
| 「それはお客様の勘違いです」 | 顧客の意見を否定し、不信感を与える。 |
| 「当社のルールなのでできません」 | 一方的な対応に感じられ、不満が増す。 |
| 「今までクレームはありませんでした」 | 他の人の例を持ち出しても、顧客の不満は解消されない。 |
| 「仕方がないですね」 | 無責任な態度と受け取られる。 |
| 「上司に確認しないと対応できません」 | たらい回しにされていると感じさせる。 |
【適切な言い換え例】
「ご指摘いただきありがとうございます。状況を確認し、対応を検討いたします」
「お客様のご意見を踏まえ、できる限りの対応をさせていただきます」
否定的な表現を避け、顧客の立場に寄り添った言葉を選びましょう。例えば、対応ができない場合であっても、「できません」ではなく、「できる限り対応します」と伝えると印象がよります。
話をさえぎる
クレーム対応では、顧客の話を最後まで聞くことが基本です。話の途中で言葉をさえぎると、相手は「自分の意見を聞いてもらえていない」と感じ、不満が増幅します。
話をさえぎると起こる問題
| 状況 | 顧客の感じること |
|---|---|
| 顧客が話している途中で「それは違います」と言う | 自分の意見を尊重されていないと感じる。 |
| すぐに「こうすれば解決します」と結論を出す | しっかり話を聞いてもらえなかったと感じ、不信感が増す。 |
| 話の途中で別の質問をする | まともに向き合ってくれないと思われる。 |
【適切な対応の流れ】
-
顧客の話を最後まで聞く
「まずはお話をお聞かせください」 -
共感を示す
「ご不便をおかけし、申し訳ございません」 -
事実を整理する
「状況を確認させていただきますので、少々お待ちください」
途中で口を挟まず、相手が話し終わるまで待ちましょう。相槌を打つことで、「きちんと聞いている」と伝わります。
たらい回し
通販のクレーム対応では、「担当部署が違う」「上司に確認する」などの理由でたらい回しにすると、顧客の不満が一気に高まります。
【たらい回しによる顧客の不満】
「さっきの人と話が違う」
「何度も同じ説明をさせられるのが苦痛」
「だれも責任を持って対応しない」
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 最初の対応者が責任を持つ | 「最後まで私が対応いたします」 |
| 社内で情報を共有する | 過去のやり取りを記録し、スタッフが変わっても同じ説明をする。 |
| ワンストップ対応を意識する | 可能な限り、1回の対応で問題を解決する。 |
【適切な対応例】
「お時間をいただき申し訳ございません。私が責任を持って対応いたします」
「別のスタッフが引き継ぎますが、すでに経緯を共有しておりますのでご安心ください」
顧客に何度も同じ説明をさせないよう、情報をしっかり引き継ぎましょう。スタッフが変わる場合でも、「引き継ぎ済みです」と伝えることで安心感を与えられます。
感情的になる
クレーム対応では、顧客が怒っていても、対応する側が感情的になってはいけません。不適切な態度をとると、さらに大きなトラブルに発展する可能性があります。
| 状況 | 起こり得る問題 |
|---|---|
| 声を荒げる | クレームが激化し、SNSなどで拡散される可能性がある。 |
| ため息をつく | 「馬鹿にされている」と感じ、不満が増大する。 |
| 高圧的な態度をとる | 企業の信用を失い、リピーターが減る。 |
【冷静に対応するためのポイント】
-
クレームを「攻撃」ではなく「要望」と捉える
「改善点を教えてくれている」と考えると、冷静になれます。 -
深呼吸して落ち着く
怒っている相手には、ゆっくり丁寧に話すと効果的です。 -
決まったフレーズを用意しておく
「申し訳ございません。対応方法を確認いたします。」と繰り返すと感情的にならずに済むでしょう。
感情的になるのではなく、「落ち着いて冷静に対処する」ことを最優先にしましょう。顧客が怒っている場合でも、あえて丁寧な言葉遣いを意識することで、自然と相手も冷静になることが多いです。
まとめ
通販におけるクレーム対応は、企業の信頼を左右する重要な要素です。適切な対応をすれば顧客満足度の向上につながりますが、不適切な対応をすると逆効果になります。特に、顧客の不満を増大させるNGワードの使用や、話をさえぎる行為は避けるべきです。
また、対応の一貫性を保ち、たらい回しを防ぐことも重要です。クレームのたびに別のスタッフへ振り分けると、顧客は不信感を抱いてしまいます。責任を持って最後まで対応する姿勢が求められます。
さらに、感情的にならず、冷静かつ丁寧な態度を貫くことで、トラブルの悪化を防げるでしょう。
クレーム対応を単なるトラブル処理ではなく、顧客との信頼関係を築く機会と捉え、誠意を持って向き合うことが成功の鍵となるでしょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。