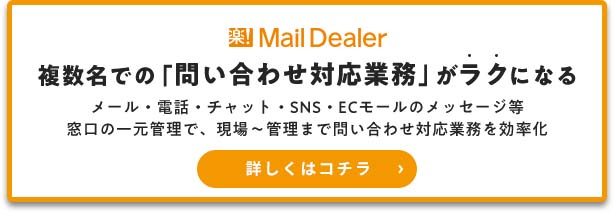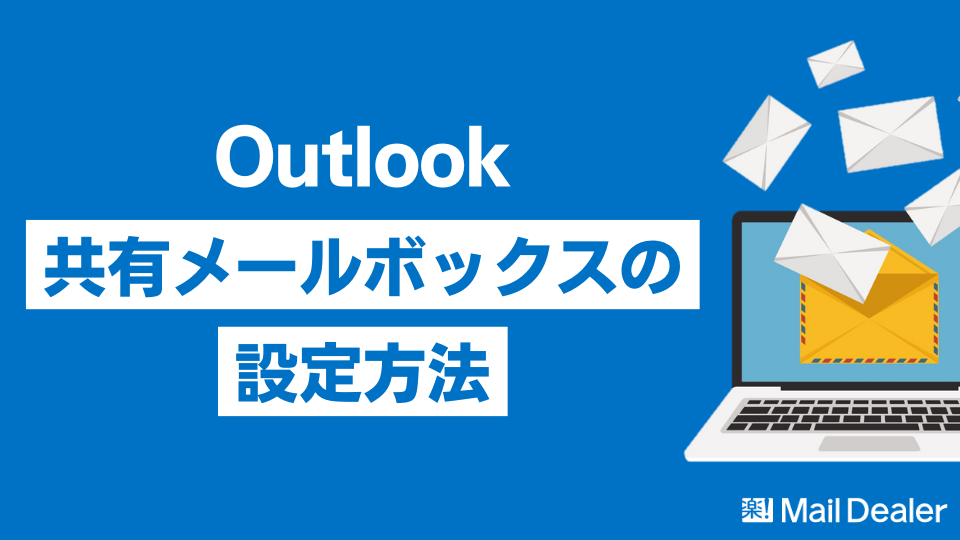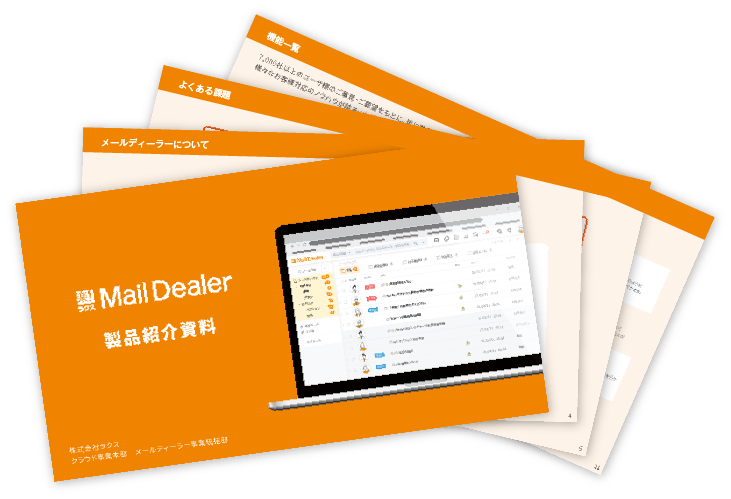コールセンターの基本業務は、お客様からのクレーム対応です。さまざまな内容のクレームに対応しなければならないため、適切な対処法を知っているか否かは非常に重要です。クレーム対応を間違ってしまった場合、会社の印象が悪くなるだけでなく、さらなるクレーム(二次クレーム)に発展してしまう可能性もあるでしょう。
この記事では、クレーム対応の基本を解説するとともに、クレーム対応でのNG行動やクレームを予防するための方法もあわせて紹介します。
クレーム対応の基本的な流れ
クレーム対応を間違ってしまうと、二次クレームに発展してしまう可能性があります。お客様が納得できるよう、正しいクレーム対応を心掛けましょう。
クレーム対応の基本的な流れは、以下の通りです。
- 挨拶・謝罪
- 事実確認・調査
- 対応策の提示・説明
- 再度の謝罪・感謝
それぞれを詳しく解説します。
1.挨拶・謝罪
お客様に対する謝罪の言葉から入りましょう。「不快な思いをしている」というお客様の心情を理解することが大事です。
ただし、謝罪の言葉だけで終わってしまっては対応としては不十分といえます。謝罪の後はお客様の話を聴き、「何が起きたのか」「どのような対応を望んでいるのか」などを正確に把握することが大切です。
また、電話での応対ではこちらの「話を聴く姿勢」が伝わりづらいため、あいづちやクッション言葉を的確に使うようにしましょう。お客様の話を聴き、適切なレスポンスを心掛ければ、「自分の話をしっかりと聴いてくれている」とお客様に安心感を抱かせることができます。
2.事実確認・調査
クレームの解決には、事実確認・調査が必須です。まずは、お客様の話から必要な事実を集め、記録していく必要があります。お客様が話す内容にはしっかりと耳を傾け、クレームの解決に役立ちそうな内容であれば、些細なことであってもしっかりと記録しておきましょう。
次に、事実確認の把握を行います。記録した事実をもとにトラブルが発生した時期や、どのようなことが起こったのか、どのような対応を望んでいるのかなどを正確に把握しましょう。クレーム内容が事実だった場合は、その責任が自社にあるのかどうかも確認するべきです。
事実確認・調査には、業務知識や一般常識が欠かせません。これらの知識・常識が欠けていると、適切な事実確認は難しいでしょう。正確な事実確認・調査を行うためにも、自身がかかわる業務の知識は積極的に身につけておくことをおすすめします。
3.対応策の提示・説明
事実確認・調査が終わったら、お客様に具体的な対応策を提示しましょう。お客様を待たせすぎないよう、迅速に対応策を提示することが重要です。
その際は、最大限の「誠意」が伝わるような対応を心掛けましょう。ただし、誠意を見せることが大事だからといって、行き過ぎた対応を行うべきではありません。対応にかかるコストや手間を考慮したうえで、社会通念や法令に則った対応を行うことが大事です。
自社に非があるのであれば、深くお詫びをして対応策を提示します。非がなかった場合は、自社の責任ではないことの説明と、不満を抱かせてしまったことについての謝罪を行いましょう。説明する際は、専門用語をできるだけ使わず、お客様に伝わりやすい言葉で伝えることを心掛けてください。
4.再度の謝罪・感謝
対応策を提示した後は、あらためて丁寧に謝罪しましょう。クレームがあった時点で、お客様からは会社への信頼を少なからず失ってしまっています。言い訳や責任逃れのような態度をとるのではなく、丁寧な謝罪で最大限の誠意を伝えて信頼回復を図ることが大切です。
お客様からのクレーム内容が、製品やサービスの改善につながる場合もあります。「貴重なご意見をありがとうございました」と感謝を伝えることも忘れないようにしましょう。クレームはお客様からの貴重な意見と捉えることもできるため、会社の財産として今後に活かしていくことができればベストです。
クレームがあったということは、お客様は自社の製品やサービスに無関心なわけではなく、少なからず期待があったことを意味します。気持ちのこもった謝罪・感謝でクレーム対応を締めくくり、会社の印象がよくなるように努めましょう。
クレーム対応でやってはいけないNG対応
クレーム対応でやってはいけないNG対応は、以下の5つです。対応を間違えてお客様を不快にさせないよう、注意しましょう。
- 言い訳や責任回避などを行う
- お客様を待たせたりたらい回しにする
- お客様の発言を否定する
- お客様の話を遮る
- 上司に相談や報告をしない
なぜこれらの行動がクレーム対応においてNGなのか、詳しく解説します。
言い訳や責任回避などを行う
クレーム対応において、言い訳や責任回避と捉えられる言動は厳禁です。たとえば「前回問い合わせをした際、担当者の対応が悪く素っ気なかった」というクレームに対して「その時期は人手が足りておらず、忙しくて対応しきれなかった」のような対応がこれに該当します。
仕方ない事情があったとしても、言い訳や責任回避は無責任な印象をお客様に与えてしまい、話がよりこじれるきっかけとなりかねません。まずは、お客様の話にしっかりと耳を傾けましょう。
お客様を待たせたりたらい回しにする
クレーム対応はできる限り迅速に行い、お客様を待たせることがないようにしましょう。電話先で待たせるのは、お客様をイライラさせる原因となります。同様に、お客様をたらい回しにするのもNGです。
どのように対応すべきかわからず他の担当者へ引き継ぐ場合は、後ほど連絡することを伝えて会話を一度終わらせたほうがよいでしょう。折り返し連絡する場合は、何時ごろ連絡するのかを伝えておくと好印象です。
お客様の発言を否定する
お客様からのクレームで会社側に非がなかったとしても、お客様の発言を否定しないようにしましょう。クレームの内容を否定するような言葉は、お客様が不快に感じてしまう可能性があり、二次クレームに発展する恐れがあります。
勘違いや間違いなど、クレームの原因がお客様側にある場合でも、肯定的なあいづちを打つように心掛けましょう。「ご不便をおかけしました」「説明不足で申し訳ございません」など、お客様の心情を考慮した言葉が適切です。
お客様の話を遮る
お客様の話を聴く中で納得できないことを言われたら、反論したくなってしまうときもあるでしょう。そのような場合でも、お客様の話を途中で遮ってはいけません。どのような内容であれ、まずはひと通り話を聴くことが大切です。
クレームという形で不満を吐き出すことで、お客様の怒りが収まる場合もあります。逆に話を遮ると怒りがヒートアップする可能性があるため、注意しましょう。
上司に相談や報告をしない
お客様からのクレームは、必ず上司に報告しましょう。お客様からのクレームが会社にどのような影響を及ぼすかは、未知数です。オペレーターだけで完結すると、会社になんらかの損害が発生する可能性があります。
どのようなクレームがあり、どのように対応したのかを詳細に上司に報告するようにしましょう。また、難しい対応を求められるクレームだった場合は、一人で抱え込まずに上司に相談することも大切です。
クレームをするお客様の心情
クレーム対応では、お客様の心情を理解することが大切です。お客様がどのような対応を望んでいるのかを把握できれば、適切なクレーム対応を行えるでしょう。クレームをするお客様の心情として考えられるのは、以下の5つです。
- 問題を解決してほしい
- 謝罪してもらいたい
- 公平に扱ってほしい
- 教えたい・改善してもらいたい
- 自分の要求を通したい
それぞれ詳しく解説します。
問題を解決してほしい
クレーム内容が「サービスが利用できなくなった」「製品の使い方がわからない」などの場合、お客様は問題の解決を求めています。お客様の話にしっかりと耳を傾け、適切な対応策を提示しましょう。具体的な対応策を提示できなかった場合、会社への失望から二次クレームに発展する可能性も考えられます。
お客様の要望自体ははっきりとしているため、お客様がなるべく速く問題を解決できるよう迅速に対処しましょう。
謝罪してもらいたい
お客様が製品やサービスを不快に感じている場合は、誠意ある謝罪を求めています。接客・問い合わせ対応中の態度や、なんらかのトラブルが発生したことによって不快な気持ちになっている場合が多いです。
仮に会社側に非がないクレームだったとしても、お客様の怒りを収めるためにしっかりとした謝罪を心掛けましょう。形だけの謝罪ではなく、お客様の心情を理解してお詫びの気持ちを伝えることが大切です。
公平に扱ってほしい
サービスを利用した際に不平等さを感じてしまった場合、お客様は「公平に扱ってもらいたい」と思っています。「自分のほうが先に注文したのに、他のお客のほうが料理が早く運ばれた」「同じサービスなのに待遇に違いを感じた」などの場面で、不平等さを感じてしまう場合が多いです。
このような場合は、しっかりとお客様の心情を理解して、丁寧な謝罪に専念しましょう。また、実際にサービスに不備があり、不平等感が生まれている可能性もあります。サービスに改善できる部分はないか、今一度対策を考えることも大切です。
教えたい・改善してもらいたい
クレームをするお客様は、「教えたい・改善してもらいたい」という親切心からクレームを入れる場合があります。このようなお客様は製品やサービスに対する自身の意見をしっかりと伝えてくれるため、クレームが製品やサービスの改善につながる可能性が比較的高いです。
クレームをお客様からの貴重な意見と捉え、お客様の言葉にしっかりと耳を傾けるようにしましょう。謝罪すべき部分に対しては謝罪をし、そのうえで「貴重なご意見をありがとうございます」と感謝の言葉を伝えることをおすすめします。
自分の要求を通したい
クレームの中には、ただ自分の要求を通したいだけのものも存在します。明確な悪意がある場合は、不当な言いがかりをつけて金銭や品物を要求されるケースもあるでしょう。
このようなクレームは一人では対処が難しい場合が多いです。上司に相談し、組織として対応してもらうとよいでしょう。自社だけでは対応が困難だと感じた場合は、警察や弁護士への相談も視野に入れておくべきです。
悪質なクレームがあった際に適切に対処できるよう、会社全体で悪質なクレームの対処法を取り決めておくとよいでしょう。
クレーム対応時の話し方・言葉遣いのポイント
クレーム対応は、顧客満足度を向上させるだけでなく、企業の信頼性を高める重要な機会でもあります。そのため、クレーム対応時の話し方や言葉遣いには特別な配慮が求められるでしょう。ここでは、クレーム対応における具体的な言葉遣いと話し方のポイントについてご紹介します。
正しい敬語を使う
第一に、正しい敬語を使うことは基本中の基本です。クレームを申し出ている顧客は、なんらかの不満やストレスを抱えています。そのような状況で、不適切な敬語や不自然な表現を使うと、顧客の不信感を高めてしまう可能性があります。
たとえば、「お客さまがおっしゃられたこと」という表現は一見丁寧に見えますが、「おっしゃる」にすでに尊敬の意が含まれているため、「おっしゃられた」は二重敬語のため不自然です。このようなミスを避けるためには、日ごろから正しい敬語の使い方を学び、自然に使えるように訓練しましょう。
また、顧客の話に対する返答にも注意が必要です。たとえば、顧客が具体的な問題を指摘してきた際には、「そうなのですね」と簡単に流すのではなく、「ご指摘いただきありがとうございます」と感謝の意を込めた返答を心がけましょう。言葉の選び方一つで、顧客との信頼関係を築くきっかけにもなります。
大きな声ではっきりと話す
クレーム対応時には、相手に伝わりやすいように大きな声で、はっきりと話しましょう。ただし、大きな声とはいえ、怒鳴るようなトーンでは逆効果になるため注意が必要です。
ポイントは、自信を持った明確な声で話します。声が小さいと、顧客に「自信がない」「誠意が足りない」と感じさせてしまう可能性があります。一方で、大きすぎる声は「威圧的」と捉えられる場合もあるため、適切な声量を心がけましょう。
また、電話での対応の場合、声のトーンが顧客に与える印象を左右します。微笑みながら話せば、自然と声のトーンが柔らかくなり、相手に安心感を与える効果があるでしょう。これにより、顧客は「真摯に対応してもらっている」と感じ、感情的になりにくくなります。
早すぎず、ゆっくりすぎないスピードで話す
話すスピードにも細心の注意が必要です。早口すぎると、顧客は内容を理解する前に不満が募り、「真剣に話を聞いていないのでは」と誤解する可能性があります。一方で、ゆっくりすぎる話し方は、「対応が鈍い」「無駄に時間がかかる」といったネガティブな印象を与える場合があるでしょう。
適切な話すスピードは、顧客が内容を把握しやすいと同時に、スムーズなやり取りを感じられるペースです。目安として、通常の会話よりもややゆっくりと話すことを心がけましょう。また、話すスピードに緩急をつければ、より伝わりやすく、顧客の記憶にも残りやすい会話が可能になります。
抑揚をつけて話す
話し方に抑揚をつければ、顧客に誠意を伝えられるでしょう。単調な口調は、相手に「型通りの対応をしているだけ」と思われるリスクがあります。特に、謝罪の言葉や感謝の気持ちを伝える際には、声のトーンや強調する言葉の意識が大切です。
たとえば、「申し訳ございません」という謝罪の言葉は、平坦に言うと形式的に聞こえますが、声に少し感情を込めるだけで、相手に伝わる印象が大きく変わります。同じように、「ありがとうございます」も、心からの感謝を表現するように抑揚をつければ、相手の心に響きやすいでしょう。
顧客の話を3分以上聞く
クレーム対応の場面では、まず顧客の話をしっかりと聞くことが最優先です。一般的に、相手の話を少なくとも3分以上聞くことで、顧客は「自分の意見を受け入れてもらえた」と感じやすくなるでしょう。この「話を聞く」というプロセス自体が、顧客の感情を和らげる効果を持っています。
顧客の話を途中で遮るのは絶対に避けなければなりません。話を最後まで聞けば、相手の不満や要望を正確に把握できるだけでなく、「適切な対応をしてもらえた」と思ってもらえる可能性が高まります。
また、話を聞いている際の態度にも注意が必要です。相づちを打ちながらうなずくことで、顧客は「自分の話を真剣に聞いてもらえている」と感じ、気持ちが落ち着きやすくなります。このような細やかな気遣いが、クレーム解決への第一歩となります。
相づちや復唱を使いこなす
クレーム対応では、ただ話を聞くだけではなく、適切な相づちや復唱を交えることが重要です。「はい」「そうですね」といった相づちを適度に使うことで、顧客は「話が伝わっている」と安心します。また、重要なポイントを復唱すれば、内容の確認ができるだけでなく、顧客の不安を軽減する効果があるでしょう。
たとえば、「○○という点でご不満があるということですね」と復唱すれば、顧客に「自分の言葉が正確に理解されている」と感じてもらえます。このようなコミュニケーションの積み重ねが、信頼関係の構築につながるでしょう。
クレーム対応時の謝罪のポイント
クレーム対応において、謝罪は顧客の不満を解消し信頼を回復するための重要なプロセスです。ただし、単に「申し訳ございません」と形式的に伝えるだけでは十分ではありません。謝罪には、顧客の感情に寄り添い、誠意を示すためのいくつかのポイントが存在します。以下では、クレーム対応時における謝罪の具体的な方法を詳しく解説します。
顧客に共感を示す
まず、謝罪の際に欠かせないのが、顧客の立場に立った共感を示すことです。クレームを申し立てる顧客は、多くの場合、怒りや不満、あるいは失望を感じています。その感情に寄り添うと、顧客は「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じ、心が和らぎやすくなるでしょう。共感を示すためには、相手の言葉や状況を具体的に繰り返し、「そのような思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした」といった言葉を用いるのが適切です。
たとえば、商品に不備があった場合、「そのようなご不便をおかけしてしまい、大変ご不快な思いをされたことと存じます」といった表現を用いれば、顧客の気持ちに寄り添う姿勢を明確に示せます。このような共感を伴った謝罪は、単に形式的な言葉を並べるだけの対応とは異なり、顧客に「誠実に対応してくれている」と感じさせる大きな効果があるでしょう。
共感を示す際に気を付けたいのは、顧客の言葉や態度に感情的に反応しすぎないことです。クレーム対応中は冷静さを保ちながら、相手の感情に配慮が求められます。「その点についてお怒りになるのはもっともです」といった表現を使えば、顧客の感情を受け入れながらも、こちらの落ち着いた姿勢を維持できます。
最初の対応が重要
謝罪の際、最初の対応が特に重要です。初動の段階で適切な言葉遣いや態度が取れない場合、顧客の不満はさらに高まり、事態がより複雑化する可能性があります。そのため、顧客と最初に接する際には、迅速かつ誠実な対応を心がけましょう。
具体的には、顧客の話を遮らず最後まで聞いた上で、速やかに「このたびはご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪の言葉を伝えます。
ここで注意したいのは、言葉に心がこもっているかどうかです。表面的な謝罪に聞こえてしまうと、顧客は「対応が形式的である」と感じ、さらに不満を抱く可能性があります。そのため、謝罪の言葉を述べる際には、相手の話をしっかり理解した上で、状況に合った具体的な言葉を添えることが求められるでしょう。
また、最初の対応では、顧客が感じている問題の深刻さに対して十分な認識を示しましょう。たとえば、「ご指摘いただいた内容は、当社にとっても大変重要な課題と考えております」という言葉を加えれば、問題を軽視していない姿勢を伝えられます。こうした対応は、顧客に「この企業は問題を真剣に受け止めている」と感じさせ、信頼を取り戻すきっかけとなります。
きれいに頭を下げる
対面でのクレーム対応では、謝罪の言葉だけでなく、適切な身振りや態度も重要です。その中でも特に重要なのが、謝罪の際の「お辞儀」です。きれいに頭を下げることは、日本のビジネス文化において、誠意や敬意を表す象徴的な行為とされています。適切なお辞儀ができるかどうかは、顧客に対する謝罪の本気度を伝える上で大きな役割を果たすでしょう。
具体的には、45度の角度で頭を下げる「最敬礼」が基本です。この最敬礼は、特に深い謝意を示す場面で使用されるものであり、クレーム対応時の謝罪においても有効です。お辞儀をする際には、視線を下に向け、背筋をしっかり伸ばした状態を保つことが重要です。また、お辞儀を終えるタイミングにも注意が必要で、相手が納得するまで数秒間姿勢を維持することが望まれます。
一方で、形式だけのお辞儀になってしまうと、逆効果になる場合もあるでしょう。たとえば、動作が雑であったり、適切なタイミングを逸してしまったりすると、「本気で謝罪していない」という印象を与えてしまう可能性があります。さらに、言葉だけが先行して、謝罪の動作が伴わない場合も、顧客に対する誠意が伝わりにくくなるでしょう。言葉と動作を一致させることが、効果的な謝罪を実現するためのポイントとなります。
謝罪の際には、表情や声のトーンにも注意を払うことが重要です。剣な表情と柔らかい声のトーンを組み合わせれば、顧客に安心感を与え、「真摯に対応してくれている」と感じてもらいやすいでしょう。特に対面の場合、視線を合わせれば誠意を伝えられます。ただし、過度に視線を固定すると、かえって圧迫感を与える可能性もあるため、バランスを保ちましょう。
クレームを減らすための対策・予防方法
ここまではクレーム対応の流れやNG行動を紹介してきましたが、クレームそのものを減らすための対策・予防もコールセンターとしては重要です。クレーム対応がオペレーターの業務ではあるものの、サービス・製品を提供する会社目線では、クレームがなるべく少ない状態が理想といえます。
クレームを減らすための対策・予防方法は、以下のとおりです。
- 製品や社員の対応などに不備が発生しないよう確認する
- 必ず情報共有を行う
- よくあるクレームや対処法を確認しておく
- お客様が自分で解決できる仕組みを作る
それぞれ詳しく解説します。
製品や社員の対応などに不備が発生しないよう確認する
お客様は、製品やサービスに不満を感じてクレームをすることが多いです。製品や社員の対応などに不備が発生しないよう確認すれば、確実にクレームを減らせるでしょう。クレームが多いとクレームの対応に工数をとられてしまうため、クレームが少なくなれば業務の効率化も期待できます。
製品の破損や汚れ、社員の態度、言葉遣いなどはとくに確認しておきたいポイントです。これらに問題があった場合は早急に改善し、お客様が不快に感じないような製品・サービスの提供を目指しましょう。
必ず情報共有を行う
お客様からのクレームに関しては、必ず社内で情報共有しましょう。情報を共有しておけば、同じようなクレームの発生や、クレーム対応時に同じ失敗をしてしまうことを防止できます。クレーム対応に失敗すると、二次クレームに発展する可能性があります。同じ失敗をしないようにすることは、会社としてとくに大切なポイントです。
情報共有すれば、クレーム対応の質も高まります。些細なクレームであっても必ず情報吸を行うようにしてください。
よくあるクレームや対処法を確認しておく
クレーム対応には、クレームの内容に応じた適切な対処が求められます。同じようなクレームが別のお客様から寄せられる場合もあるため、落ち着いて対処できるよう、よくあるクレームや対処法を事前に確認しておきましょう。
先述したように、クレーム対応で失敗すると二次クレーム発生の要因となりえます。対処法を事前に確認しておけば、二次クレームの発生を抑制可能です。二次クレームが少なくなれば、結果的にクレームの総数も減少します。マニュアルがあればマニュアルを確認し、マニュアルがない場合は上司にクレームごとの対処法を確認してください。
お客様が自分で解決できる仕組みを作る
「サービスが利用できなくなった」「製品の使い方がわからない」など、サービスや製品を利用するうえで問題があった場合、クレームが発生することが多いです。このようなクレームは、「製品の説明書やWebサイトを確認しても問題が解決しなかった」ことが根本的な発生要因であるため、お客様が自分で解決できる仕組みを作ればクレームを減らせます。
よりわかりやすくなるよう説明書の文言を改善するほか、Webサイトによくある質問を掲載する・チャットボットを導入するなども効果的です。
お客様と向き合い丁寧に対応しよう
クレームの多くは、お客様が製品やサービスに不満を感じることで発生します。クレームによっては会社側に非がない場合もありますが、そのようなときも誠意ある態度でお客様と向き合いましょう。お客様の話を遮ったり、否定したりしてはいけません。
会社全体として、クレームを減らすための対策に取り組むことも大事です。製品や社員の対応を見直し、お客様が不快に感じるような場面を極力減らしましょう。
メールディーラーではお役立ち資料として「クレーム対応マニュアル」を提供しています。クレームの対処方法や具体的なお詫びメールの書き方などが記載されているため、興味がある方は下記フォームをご覧ください。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。