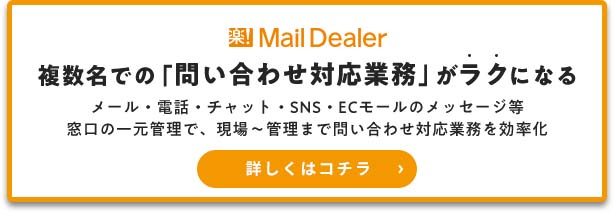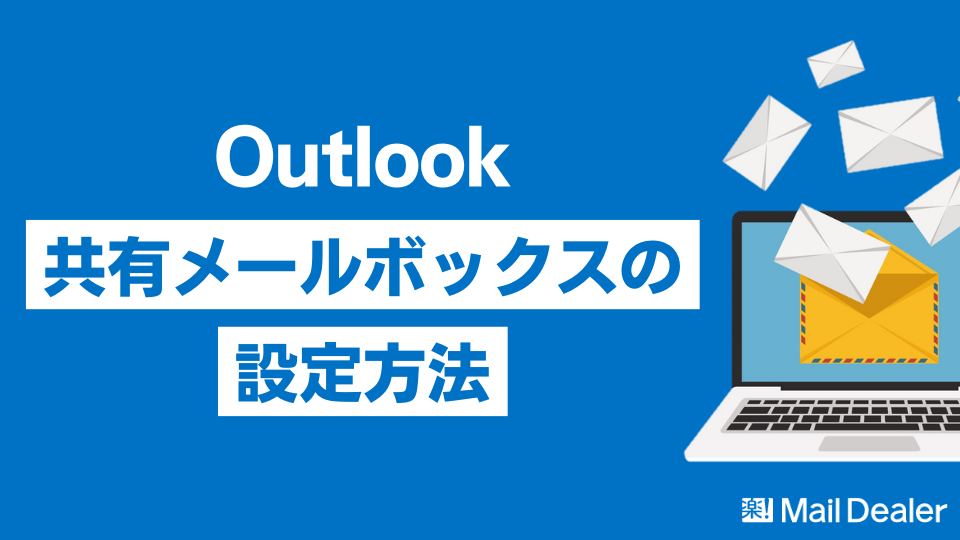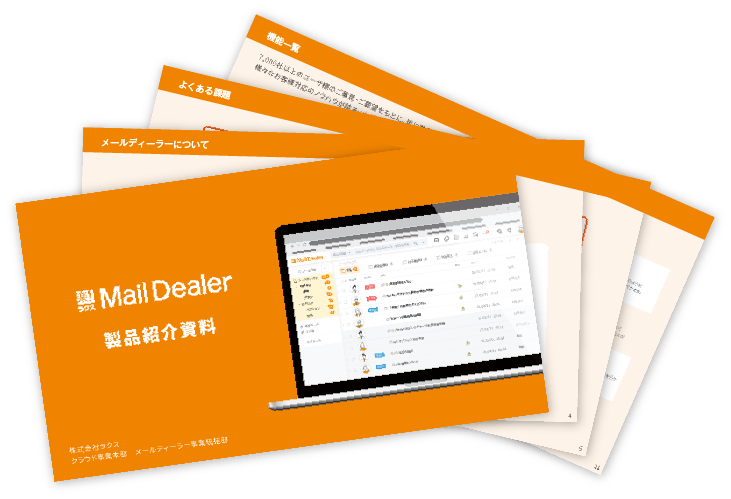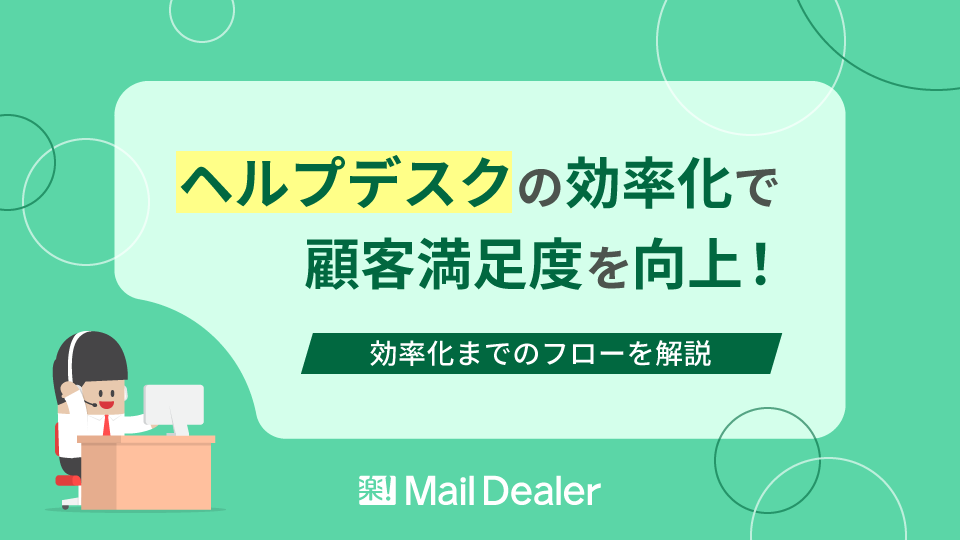
現代のビジネスにおいて、ヘルプデスクの役割はますます重要になっています。顧客やスタッフからの問い合わせに迅速かつ正確に対応することは、顧客満足度・業務効率の向上に直結します。しかし、問い合わせが増加する一方で、人手不足や対応品質のばらつきなどが原因で、顧客に不満を感じさせてしまう本末転倒なケースも少なくありません。
本記事では、ヘルプデスクが抱える典型的な課題を明らかにし、それらを解決するための効率化の方法を詳しく解説します。
ヘルプデスクとは
まず、ヘルプデスクの基本的な役割を確認しましょう。ヘルプデスクとは、顧客やスタッフなど、社内外からの問い合わせを受け付け、問題解決を支援する窓口のことを指します。
その業務は、単なるサポート業務にとどまらず、企業全体の効率化やブランドイメージ向上にもつながります。
社外ヘルプデスク
社外ヘルプデスクは、主に顧客からの問い合わせ対応を担当します。製品やサービスに関する質問、トラブル対応、購入後のサポートなどがその範囲です。
通信機器の不具合に関する相談を受け付けたり、ソフトウェアの使用方法について指導したりと、顧客の不満・疑問を解消し、満足度を向上させることが目的です。
社外ヘルプデスクは、企業の「顔」としての役割を果たすため、迅速かつ的確な対応が求められます。対応の品質が顧客満足度を左右するといっても過言ではないため、担当者による質のバラつきは起こらないよう対策が必要です。
社内ヘルプデスク
一方、社内ヘルプデスクは、従業員からの問い合わせ対応を担当します。
社内システムのトラブル対応、機器の操作説明、人事関連の手続きなど、業務に関するトラブルや疑問を解消することが目的です。
従業員が業務を円滑に遂行できるよう支援することで、業務効率低下を予防でき、企業全体の生産性が高まります。特に、リモートワークが普及した昨今では、遠隔でのサポート体制を整える必要性が高まっており重要な役割を担っているといえるでしょう。
ヘルプデスクによくある課題
ヘルプデスクは、顧客満足度やスタッフの効率性に直結する重要な業務です。
しかし、その現場は多くの課題に直面しています。それらの課題を解決せずに放置すると、問い合わせ対応の品質低下やスタッフの負担増加につながり、結果として顧客の不満を引き起こし、販売数の下落・解約の増加などに繋がる恐れがあります。
では、ヘルプデスクに生じがちな課題とは一体どのようなものなのでしょうか?具体的に見ていきましょう。
問い合わせが多い
1つ目は、ヘルプデスクに寄せられる問い合わせが、対応人員に対して過剰な数になってしまう場合です。この課題は非常に多くの課題が抱えている課題でしょう。
商品力やサービス力の向上を目指し、機能を複雑化するにつれて、利用者の理解が追いつかなくなってしまっていることが原因と考えられます。その結果、利用者の疑問から生じる問い合わせが増加し、ヘルプデスクの工数の圧迫、それによる対応品質の悪化に繋がり、結果として顧客の満足度・従業員の業務効率が低下してしまいます。効率や満足度の向上を目指した結果、真逆の方向に向かってしまう悪循環と言えるでしょう。
また、特定の時間帯への集中も課題として抱えている企業は実際多いです。
たとえば、営業開始直後や昼休みなど、利用者が比較的自由に時間を使えるタイミングに多くの問い合わせが重なるため、待ち時間が長くなり不満に繋がるケースは存在します。このような状況では、優先度の高い問題の対応が遅れる可能性があり、クレームの発生や利用者の不満を招く要因となるでしょう。
問い合わせ数の多さを改善するには、顧客や従業員が自身で解決できる環境を整えることが重要です。
FAQページやチャットボットが代表例で、ヘルプデスクの工数を抑えたうえで、疑問や不満を解消できる仕組みを取り入れましょう。
利用者が自己解決できる仕組みを構築すれば、問い合わせ件数の削減を図れるでしょう。こうした取り組みによって、スタッフがより複雑で重要な案件へ集中することが可能になります。
人手不足
人手不足は、ヘルプデスク運営における深刻な課題の一つです。問い合わせ件数の増加に対して十分な人数を確保できないと、スタッフの負担が増大し、最終的には対応スピードの低下や品質の悪化を招きます。しかし、ヘルプデスクの人員を増加すると、人件費が利益を圧迫してしまうため、課題を認識しつつも、人員増加に踏み出せない企業も多く存在します。
課題に対応するためには、スタッフの負担を軽減するためにシステムを導入するなどの対応や、限られた人材を有効活用する仕組みの整備が必要です。たとえば、AIや自動化ツールを導入することで、単純な問い合わせへの対応工数を削減するなどが手段として挙げられます。また、一部アウトソーシング(外部委託)を活用して業務の一部を外部に委託することで、内部リソースを重要な業務へ集中させつつ、採用よりも低いこすとで対応工数を確保することも効果的です。
担当スタッフの知識不足
ヘルプデスクのスタッフが十分な知識を持たない場合、迅速かつ正確な対応が難しくなり、回答内容の確認などで余計な工数が増加してしまうということも起こりがちです。
このケースは、新製品の導入やサービスのアップデート時に特に増加し、適切な研修や教育が行われていない場合、スタッフは問い合わせ内容に対して不適切な回答をしてしまい、顧客の満足度を低下させてしまうことに繋がります。
知識不足は、経験の浅いスタッフが多い場合や、製品やサービスが複雑化している場合に生じやすいです。この状況を改善するには、業務に必要な知識をインプットするための研修や、一度発生した問い合わせ内容への回答をテンプレート化し、チームで共有する体制を整えるなどが主な手段として挙げられます。
対応品質を平準化!対応のテンプレート共有は「メールディーラー」
ナレッジ・ノウハウが蓄積されない
ヘルプデスクにおいて日々の業務を通じて得られるナレッジやノウハウを組織全体で共有することは、各種業務の効率化において不可欠です。このような知識が適切に蓄積されていない場合、同じ問題が繰り返し発生したり、新人スタッフが対応に苦慮するケースが増加します。特に、属人的な対応が多い場合、特定のスタッフに依存する体制が生まれ、業務の継続性が損なわれるリスクが生じます。
この課題に対応するには、問い合わせ内容や対応履歴を一元管理できるシステムの導入が効果的です。また、マニュアルの整備や更新を定期的に行い、新しい情報を迅速に共有する体制を整えましょう。これにより、スタッフ間で知識を共有しやすくなり、対応の均一化と効率化を実現できます。
対応履歴をチームで簡単共有!問い合わせ対応の効率化は「メールディーラー」
対応速度が遅い
ヘルプデスクの対応に時間がかかりすぎる場合、顧客や従業員の満足度が低下します。
特に、迅速な対応を求められる場面で遅れが生じると、不満やクレームの増加に直結する恐れがあります。解決には、問い合わせ内容を優先順位に基づいて分類し、緊急性の高い案件に迅速に対応できる体制を整える必要があるでしょう。
また、業務時間外に発生する問い合わせは、利用者にとって重要な問題を迅速に解決できない要因となりえます。対応するには、24時間対応可能なチャットボットや自動応答機能を導入し、基本的な質問に迅速に対応する仕組みを整えることが必要です。また、翌営業日に確実に対応を行うためのフォローアップ体制の整備も重要です。
具体的な解決方法は、下記の記事で解説しています。是非ご覧ください。
ヘルプデスクを効率化する手順
ヘルプデスク業務を効率化するためには、単に新しいツールを導入するだけではなく、現状をしっかりと分析し、課題に適した解決策を見出し、継続的な改善の積み重ねが重要となります。
ヘルプデスクの効率化を進めるための基本的な手順を押さえておきましょう。
1.問い合わせ内容を分析する
まずは、問い合わせ内容の徹底的な分析を行いましょう。問い合わせの種類や頻度を把握することで、どのような問題が多発しているのか、特に対応が遅れている領域はどこなのかを明確にできます。
そのうえで、見えてきた問題は何で解決できるのかを見極めます。
問い合わせ内容の分析には、定量的なデータの収集と定性的な検討の両方が必要です。たとえば、一定期間内に寄せられた問い合わせ件数を確認し、そのうちどのようなテーマが多かったかを割合で示し、スタッフの記録や利用者のフィードバックを通じて、対応に苦労した事例や特に満足度が低かった場面についての情報を収集します。
結果、どの分野を重点的に対処すべきかを特定できるでしょう。
2.問い合わせ内容のカテゴリー分け
問い合わせ内容を効率的に分析するためには、カテゴリー分けが不可欠です。
たとえば、「製品の使い方」「トラブルシューティング」「購入や契約に関する質問」「その他一般的な質問」といった大分類を作成し、さらにその中を細分化すれば、問い合わせの全体像をより詳細に把握することが可能になります。
このように分類されたデータは、スタッフのトレーニング計画やFAQの作成に活用できるだけでなく、特定の領域における問題を解決するための具体的な施策立案にもつながるでしょう。
3.解決方法を検討する
問い合わせ内容を分析して課題が明確になったら、それに応じた解決方法を検討します。現状の課題に適切に対応するための具体的な施策を立案し、解決できる見込みがあるか、費用対効果が許容範囲内かどうかを重点的に見ていきましょう。
解決方法の検討では、効果検証を柔軟に行えるようにするため、短期的な施策と長期的な施策のバランスを取りつつ実装しましょう。
短期的な施策の代表例は、すぐに導入可能なツールやテンプレートの活用が挙げられます。たとえば、よくある質問への回答を迅速に提供するために、テンプレート化された返信を用意することや、簡易的なFAQページの設置といったようなものです。
一方、長期的な施策の代表例は、ナレッジ共有システムやAIを活用した問い合わせ対応の自動化、スタッフのスキル向上を目的とした研修の充実など、組織全体で取り組む施策などが挙げられます。
さらに、解決策を実行する際は、各施策の効果を測定するための指標の設定が重要です。問い合わせ件数の削減率、対応スピードの向上、顧客満足度の変化など、具体的な成果を数値で示せば、施策の有効性を客観的に評価しつつ、柔軟に対応しましょう。
4.PDCAを回転させる
効率化は一度の取り組みで完了するものではなく、トライアンドエラーを重ねる施策と言えます。一度導入した解決策が時間の経過とともに効果を発揮しなくなるケースもあり、PDCAを常に回すことが重要です。
上手くPDCAを回すには、
- 明確な判断指標を定める(一人当たりの月間対応件数を10%削減など)
- いつ効果測定を行うか事前に定める(実装後1ヵ月を検証機関とするなど)
といった先を見据えて施策を実行に移しましょう。やって終わりの施策にしない行動が非常に重要です。
さらに、見直しと改善のプロセスを定期的に繰り返せば、業務プロセスそのものが洗練されていく場合がほとんどです。
ヘルプデスクの効率化の方法・施策
ここからは、効率化を推進するために有効な取り組みを紹介します。これらの施策を組み合わせて活用すれば、業務全体の効率化が進むだけでなく、顧客やスタッフの満足度も向上するでしょう。
対応範囲を明確に設定する
効率的なヘルプデスク運営を目指す上で、対応範囲の明確化は非常に重要です。問い合わせ対応において、何をサポートするのか、何を他部署に引き継ぐのかを明確にすれば、スタッフの混乱を防げるでしょう。たとえば、製品に関する技術的な質問はヘルプデスクが対応し、契約内容の変更や請求関連の問い合わせは営業部門が担当する、といった役割分担を文書化してその通り業務を推進していくことで、特定の部門だけが業務過多になるといったことを予防することが可能です。
対応範囲が曖昧な場合、スタッフが無駄な対応を行うことになり、結果的にリソースの浪費につながります。対応範囲を明確にすれば、対応スピードが向上し、問い合わせ件数の分散化も期待できるでしょう。この取り組みは、特に複数のチームが関連する業務プロセスにおいて効果的です。
対応マニュアルを作成する
対応品質のバラつきが問題視されている場合には、対応方法を統一することを目的としてマニュアルの作成・活用が効果的です。
マニュアルは、対応品質を均一化するだけでなく、新入社員が戦力化するまでのスピードを早める効果も期待できます。問い合わせの内容に応じた対応のテンプレートを用意することで、従業員が迅速かつ正確に対応できるようになるでしょう。
また、マニュアルは定期的に見直しを行い、更新することが重要です。新しい製品やサービスが追加された際は、応じて問い合わせ内容の種類も増加するためです。
さらに、スタッフの意見やフィードバックを取り入れることで、実際の業務に即した内容に改善でき、問い合わせ対応時のやり取りの数の削減が見込めるでしょう。マニュアルの整備は時間と労力がかかるものの、長期的には大幅な業務効率向上が期待できます。
マニュアルの作成については、下記の記事で詳しくまとめているので是非ご覧ください。
返信用テンプレートを作成する
問い合わせ対応の中には、1つの回答内容でカバーできるケースが多々あります。このような場合、返信用テンプレートを作成し、ヘルプデスクチーム内で共有し使用することで、対応にかかる時間を大幅に短縮することが可能です。テンプレートには、標準的な挨拶文や回答文をあらかじめ用意しておき、必要に応じて内容を少し修正するだけで送信できるように設計しましょう。
テンプレートを作成する際は、過去の対応履歴を参考に実際の問い合わせ内容に基づいたものにしましょう。また、テンプレートが硬すぎたり、汎用的すぎたりすると、利用者に機械的な対応を受けたという印象を与え、サポートを受けているという実感を薄めてしまいます。
そのため、人対人であるということをアピールできるような構成で作成するとより効果的です。
また、やり取りの回数を減らすため、少ないやり取り回数で解決に導くように意識するとベストです。
対応品質を平準化!対応のテンプレート共有は「メールディーラー」
メール共有管理システムを導入する
ヘルプデスクにおけるメール対応を効率化するには、メール共有管理システムの導入が効果的です。このシステムを活用すれば、複数のスタッフがリアルタイムでメールのステータスを把握し、対応状況の重複や漏れを防げます。特に、大量の問い合わせを処理する環境では、メール共有管理システムの有無が業務効率に大きく影響するでしょう。
また、このシステムには、対応内容を自動的に記録する機能が備わっている場合が多く、ナレッジの蓄積にも役立ちます。スタッフ間で情報を共有しやすくなるため、チーム全体の対応力が向上し、顧客満足度の向上につながります。
FAQページを作成する
問い合わせを削減する手段として、FAQページの作成は非常に効果的です。よくある質問とその回答を整理し、利用者が簡単にアクセスできるようにすることで、自己解決を促し、問い合わせ数の削減が期待できます。
特に、基本的な操作方法や設定手順など、問い合わせ頻度が高い内容を網羅したFAQページは、ヘルプデスクスタッフの大きな負担軽減が見込めるでしょう。
FAQページは、定期的に内容を見直し、利用者のニーズに合った情報を提供することが重要です。また、わかりやすく整理されたカテゴリーや、検索機能の充実も利用者の利便性を高めるポイントです。
チャットボットを導入する
最近では、チャットボットの導入が注目されています。AIを活用したチャットボットは、24時間体制で利用者の問い合わせに対応できるため、業務時間外の負担を軽減します。さらに、基本的な問い合わせに自動で対応すれば、スタッフが複雑な案件に集中できる環境を作り出せるでしょう。
チャットボットを導入する際は、初期設定に十分な時間をかけましょう。想定される質問と回答をできるだけ多く登録し、利用者がスムーズに解決できるように設計します。また、チャットボットが対応できない場合は、迅速にスタッフに引き継ぐ仕組みを整えましょう。
チャットボット導入に関する詳しい記事は、以下をご覧ください。
AIを活用する
AIは、問い合わせの内容を解析し、最適な回答を提供するための強力なツールです。自然言語処理技術を用いたAIは、問い合わせ内容を理解し、適切な情報を迅速に提示できます。また、過去の対応履歴を学習させれば、次回以降の問い合わせに対する精度が向上するでしょう。
さらに、AIを活用すれば、データ分析も効率化できます。たとえば、問い合わせ傾向を自動的に抽出し、予測分析を行えば、事前の準備や対応策を立てられるでしょう。
問い合わせ管理ツールである「メールディーラー」では、AIを活用した「AIクレーム検知機能」が利用できます。
AIが問い合わせメールの文言や表現から問い合わせユーザーの感情を読み取り、優先的に対応する必要があるものかどうかを自動で判断してくれる機能です。
こういったAIによるサポートは、対応品質の向上や、業務工数の削減が大きく期待できるため、検討の優先度は高いと考えていいでしょう。
スタッフ研修を強化する
スタッフのスキル向上は、ヘルプデスク全体の効率性と対応品質を高めるために欠かせません。具体的な事例を交えた研修や、顧客対応のシミュレーションを通じて、スタッフの実践力を養いましょう。また、定期的なトレーニングを行い、新しい製品やサービスについての知識を常にアップデートすることが重要です。
アウトソーシングを活用する
対応リソースが不足している場合は、アウトソーシングの活用を検討します。専門のサポート企業に一部業務を委託すれば、内部リソースを効率的に活用できるようになるでしょう。アウトソーシングを選択する際は、業務範囲や品質基準を明確にし、綿密な連携を図ります。
これらの施策を適切に組み合わせれば、人員を採用するよりもコストを抑えつつ、ヘルプデスクの効率化を実現し、顧客満足度や業務効率の向上を実現できるでしょう。
まとめ
ヘルプデスクの効率化は、業務負担の軽減や顧客満足度の向上に直結する重要な取り組みです。対応範囲の明確化やマニュアルの整備といった基本的な施策から、チャットボットやAIの活用といった最新技術の導入まで、多角的な方法が存在します。これらを適切に組み合わせれば、問い合わせ対応の迅速化やナレッジの蓄積が進み、結果的にヘルプデスク全体の品質向上が期待できます。また、定期的な見直しやスタッフのスキルアップも忘れてはなりません。
効率化は一度の施策で完結するものではなく、継続的な改善が求められるプロセスです。各企業の状況に応じた最適な方法を採用し、業務の効率化を図りましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。